図形の学びは、小学校中学年から本格的に始まりますが、そこでつまずいて「算数嫌い!」となる子も少なくありません。そのような事態を避けるためには、幼児期から図形に親しむことが大切です。
今回は、家庭で図形センスを伸ばすために親御さんが知っておきたいことや、具体的な取り組み方を年齢別に紹介します。これを参考に、子どもの学びをサポートしましょう!
図形が子どものIQに与える影響

これまでの記事で、IQ(知能指数)は5つの要素に支えられていると説明してきました。
- 記憶力
- 思考力
- 概念センス(表現力や語彙力)
- 図形センス
- 記号的センス(数、色の理解)
参照:IQの高い子どもを育てる!知育(知能教育)は家でできる!
その中でも、図形センスは特にIQ値に大きく影響します。図形センスが豊かな子どもは、IQが高く出る傾向があります。逆に、図形に苦手意識があるとIQの数値もあまり伸びません。幼児期から図形に触れることが、子どもの知能発達にとって非常に重要なのです。
では、どのように図形センスを育てればよいのでしょうか?
図形センスとは何か?
図形センスとは、単に形を見分ける能力ではありません。空間を把握し、物体を頭の中で自由に動かしたり変形させたりする空間認識力のことです。例えば、図形を頭の中でイメージし、回転させたり、分割して新しい形を作ったりする力です。この力がついてくると、複雑な問題にも柔軟に対応できるようになります。
具体的には、図形をじっくり観察して、どう動かすかを考えられる力と言えるでしょう。この力は、年齢によって伸びる部分が異なるので、適した学びが必要です。


もっと簡単に言うと、「図形をじっと見て、どうすれば良いか考えられる」ってことですね。年齢に応じて「どうすれば良いか」の問題部分は変わりますので、後述します。図形が得意な子どもは、図形全体を捉えられる子が多いです。部分的な形に囚われず、全体をよく見てイメージし、図形を動かす。それが出来ている子を見ると、「図形のIQ値高いな」と思います。
図形センスを育てるための3つのポイント
ここまでの話で「じゃあさっそく図形パズルやプリント・ドリルを買ってきて、子どもに学習させようじゃないかー!」と意気込む方もいらっしゃるでしょう。その前に、次のことを知っておいてください。
1. 図形は「経験」で養われる
リンク
図形センスは、日常的にさまざまな図形に触れることで養われます。特に8歳までに多くの図形に触れることが重要です。プリントやドリルを使うよりも、まずは実際の物体を使った図形遊びから始めましょう。
例えば、積み木やパズルを使って図形に親しむことで、視覚的に理解しやすくなります。三角形を二つ組み合わせて四角形を作るなど、具体的な形を体験することで、子どもの空間認識力は大きく育ちます。

2. 年齢に応じた「楽しい」学びを提供
リンク
学習は楽しさが重要です。年齢に応じた適切なレベルの図形遊びを提供することで、子どもが「もっとやりたい!」と思うようになります。
例えば、パズルや積み木など、子どもが自分で達成感を味わえる遊びを用意しましょう。親は必要以上に口出しせず、適切なヒントを与え、子ども自身で考えて解決できるようにサポートすることが大切です。
3. 図形センスを伸ばすのは「8歳まで」がカギ
IQの伸びは8歳までが非常に効果的だと言われています。特に11~12歳頃には、IQの伸びが止まるともされています。このため、図形センスを育てたいなら、8歳までにしっかりと図形に触れさせることが大切です。

もちろん、12歳以降に猛勉強により知識を獲得することはできますが、イメージする力や頭の中で図形を操る力は育ちにくいです。いわゆる「頭の固い」状態になってしまいます。図形を得意な子に育てたいなら、図形を苦手にさせないためには8歳まで適齢の図形問題に触れさせていきましょう。
年齢別に見る図形センスの育て方
年齢に見合わないただただ難しい、親御さんに「わぁこんな難しいことしてるのね♫」と言われたいだけの問題をさせてもあまり良いことはありません。残念ながら、そんなものは百害あって一利なし。「図形って難しいんだ…」という印象や苦手意識しか与えません。それでは、年齢に見合った問題に即した図形問題を見ていきましょう。
【3歳児向け】基本図形の理解とパズル遊び
ステップ1: 丸、三角形、四角形などの基本図形を覚える
ステップ2: 三角形2つで四角形を作るなど、簡単なパズルに挑戦
ステップ3: 動物や物のシルエットから形を当てる遊びを通じて、形の認識を深める
【4歳児向け】複雑な形と立体への挑戦
ステップ1: 台形やL字型など、基本図形以外の形にも挑戦
ステップ2: 積み木を見本を見ながら作る
ステップ3: 枠のない状態でのパズルに挑戦し、空間認識力を育む
【5歳児向け】図形の応用と平面パズル
ステップ1: 複雑なパズル(線だけのものや折り込むもの)に挑戦
ステップ2: ピースを動かして形を完成させるパズルを使う
ステップ3: 縮小図を見て異なるサイズの図形を完成させる
【6歳児向け】立体図形の理解と展開図
ステップ1: 平面図形から立体図形を作る(展開図から立方体など)
ステップ2: 立体パズルに挑戦し、空間把握力を強化
ステップ3: 絵を見て、積み木が何個あるかを当てる
ステップ別にしてますが、得意不得意があるので順番でなくても良いと思います。年齢はあくまで目安。もし図形が既に得意でどんどん先に挑戦できるなら、難しすぎない程度に先を挑戦してみてください。逆に、年齢より遅れてるように感じても気にしないこと。

8歳まで時間はたっぷり。じっくり取り組んで頂きたいものです。年齢別の問題やステップを箇条書きにしてみましたが、実際にどんなものがいいのか、知育玩具、おもちゃ、プリント、アプリのおすすめリンク紹介はこちら↓↓
図形が得意な子どもに育てる!年齢別:幼児期におすすめのおもちゃ教材
年齢別でおもちゃを買うと部屋が大変なことに…という方はレンタルもおすすめです↓↓
図形センスを伸ばすためのポイント
幼児期にさまざまな図形に触れることで、子どもの図形認識力や空間把握力が育まれます。年齢に合った適切な図形遊びや問題に取り組むことで、楽しく学びながら図形センスを養うことができます。
家庭でできる図形学習を続けて、子どもが「図形が楽しい!」と思えるようにサポートしていきましょう!
前回記事:子供のIQが分かる!自宅で無料【幼児~小学校用】IQテスト知能検査とは
次回記事:子どもを図形好きにする!【年齢別】幼児教室講師おすすめ知育玩具・おもちゃ
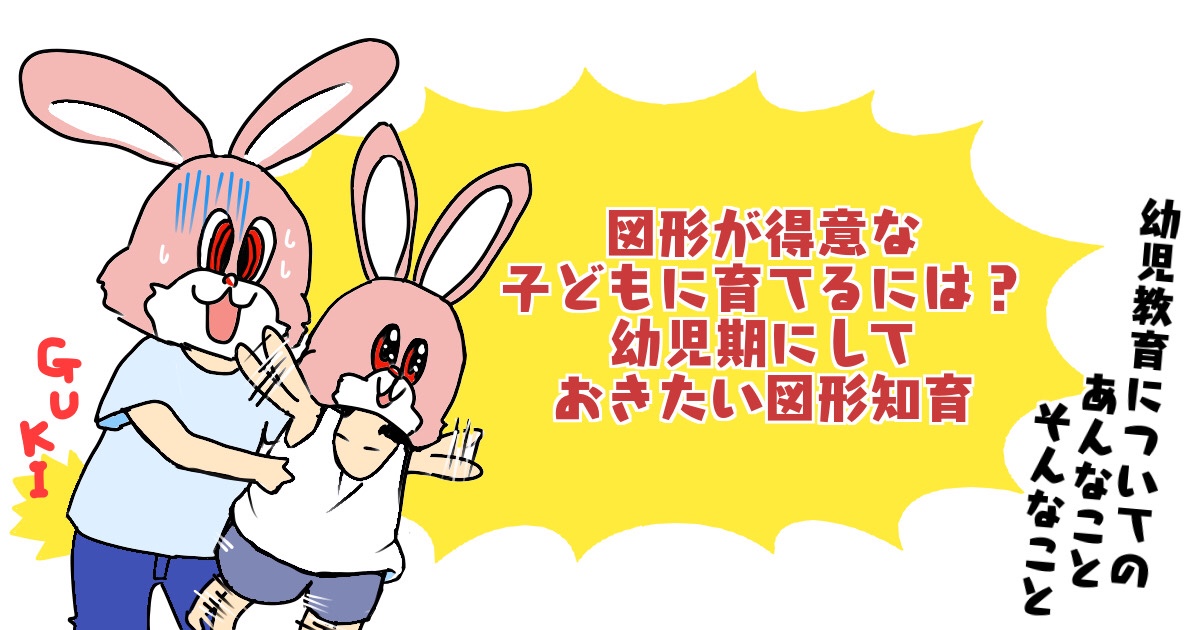



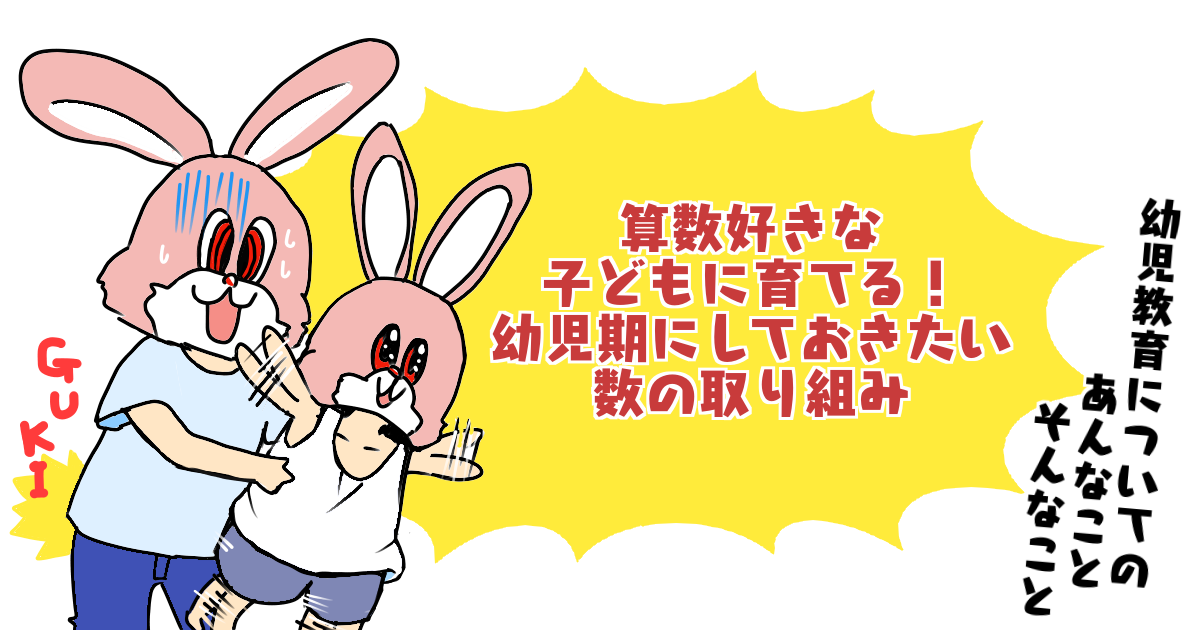
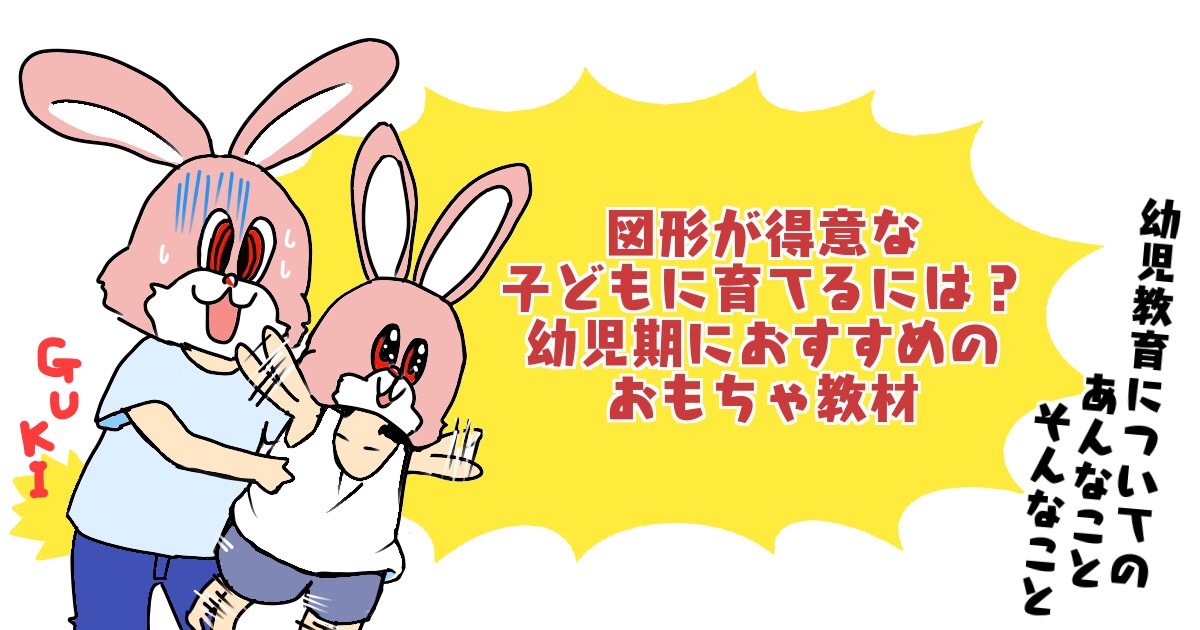
コメント