幼児の図形センスを育む知育玩具・パズル・アプリとは
前回の記事では、幼児期における図形センスの重要性についてお伝えしましたが、実際にどのような知育玩具や教材を使えばよいか悩む方も多いのではないでしょうか。
参照:【年齢別・図形問題】図形が苦手な子供にしない!学習前の鉄則
今回は、年齢ごとにおすすめの図形遊びに役立つ知育玩具や教材を紹介します。また、無料でダウンロードできるインターネット教材もまとめています。お子さんの成長に合わせて、楽しく図形に触れられるアイテムを取り入れてみましょう。
【0歳〜3歳】基本図形に親しむ
3歳までの時期は、まず基本的な図形(丸・三角・四角)に触れることが大切です。平面パズルや積み木を使って、図形感覚を自然に養いましょう。
おすすめ図形遊び:積み木
対象年齢:1歳~
丸や三角、四角などの基本図形が揃った積み木は、図形遊びの基礎を築くアイテム。形を分類したり、数を数えることで知育効果も抜群です。
おすすめ図形遊び:基本図形のパズル
対象年齢:3歳~
三角形を使ったパズルは、形を組み合わせる楽しさを教えてくれます。見本通りに作るだけでなく、自由に形を作らせてみるのも良いですね。
おすすめ図形遊び:シルエット当てゲーム
ちびむすドリル
色もヒントもないシルエットから形を当てる遊びは、図形認識力と推察力を鍛えます。親子で一緒に楽しめる活動です。
【年少3歳~4歳】複雑な図形に触れる
年少さんになると、基本図形に加え、より複雑な図形(平行四辺形や台形)にも触れさせましょう。遊びを通じて様々な形に挑戦し、図形感覚を広げていきます。
積み木遊び(対象年齢:3歳~):見本の平面図を見ながら、立体物を積み上げる遊びは、空間認識力を育てます。

複雑な図形遊びに最適。優しいレベルから難しいレベルまで揃っているので、ステップアップしやすいパズルです。優しいもの~難しいものでレベルに合わせやすいです。最初の③くらいまでは未就園児でも挑戦できます。
おすすめ図形遊び:枠なしで見本通り机上に作る
対象年齢:3歳~
枠なしで作る。これができたら図形的能力はかなり進んでいます。こちらは、問題がたっぷり77つあるタングラムパズル。初めは枠内に作り、後から枠外に見て作れるようになれればバッチリです!
おすすめ図形遊び:キューブ
対象年齢:3歳~
平面の見本を置いた状態で立体を同じように作るのは、子どもにとって難しいことです。くもんのキューブ積み木は、平面パズルとして遊ぶこともできるので、段階を経て立体に移行できます。積み木を積んだ後は何個でできたか聞くようにしてくださいね。
おすすめ無料アプリ:幼児学習ゲーム
形や大きさ、色に関する問題が詰まった無料アプリ。遊び感覚で学べるので、お子さんが楽しく続けられます。
幼児学習ゲーム(形、大きさ、色)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bomsoft.matchs
幼児期に絶対経験したい形、大きさ、色の問題がたっぷりの無料アプリ。楽しく学べるツールです。
いくつあるかな?https://fantamstick.com/psg/howmanyblocks
こちらは立体図形の幼児向け学習アプリ。数を数えることに特化しているため、立体の数的理解にも繋がります。
【年中4歳~5歳】平面から立体へ発展
年中さんになると、より高度な図形問題にも取り組めるようになります。平面図形を頭の中で動かしたり、立体図形を理解する力を養いましょう。
おすすめ図形遊び:複雑な図形パズル
対象年齢:4歳~
初めて見る形状のパズルでも、この時期の子どもは楽しみながら挑戦できます。平面と立体の両方で遊べるパズルを選ぶのがおすすめです。平面から立体まで遊べるので、徐々に立体を取り入れる意味でGOOD。
おすすめ図形遊び:移動パズル
ちびむすドリル

こちらはプリントドリルです。図形を頭の中で移動させ、結合する遊びは、図形認識力をさらに高めます。4歳頃から少しずつドリルを取り入れるのも◎2つの図形を頭の中で移動させてくっつけるという操作が必要です。
難しいようなら図形を切り取って、実際に手を動かして作らせましょう。その他、タングラムパズルがいっぱいあるなら、親御さんが適当に作った図形Aから1個動かした図形Bを見せるというのもOK。子どもにはAを作らせた後、Bの見本を見せながら「1個だけ動かしてBにしてね」と設問します。
おすすめ図形遊び:サイズの違う図形
対象年齢:3歳~
見本が縮図になっているものを実際に自分の持つ大きさで作る。大人には簡単ですが、子どもにとっては難易度が高いものです。今まで枠内に入れる形でパズルをしていたお子さんなら特に。タングラムを既にお持ちなら、見本を縮小コピーしたり、親御さんが作った図形を写真に撮って見本にすれば良いので、買い直しは必要ありません。
【年長5歳~6歳】平面図形から立体図形へ
年長さんになると、平面図形を立体に変換したり、立体図を平面に戻す問題に挑戦できるようになります。この時期は、立体図形を作る遊びを取り入れてみましょう。
おすすめ図形遊び:立体マグネット
対象年齢:6歳~
立体を作る際に役立つマグネットブロック。平面展開図から立体へと組み立てる操作を経験することで、空間認識力がさらに深まります。最初から立体を組み立てる子どもが多いと思いますが、年長さんになったら、まず平面を作り(展開図)組み立てて立体にするという操作も経験して頂きたいもの。
観覧車や車などを作るのももちろん良いですが、ガイドに簡単な立方体や三角錐などの展開図がのっているので、そちらも作らせてみましょう。それか、よくある展開図を切り取ってサイコロを作るなどしても良いですね。
おすすめ図形遊び:動かす立方体パズル
対象年齢:5歳~
立体を動かす力を鍛えるパズル。ドリルで行うだけでなく、親が一部を動かして見せ、それを再現する遊びも図形の理解を促進します。たとえば、親御さんが積み木で1つの立体Aを作り、そこから1個だけ動かした立体Bを見せます。子どもにはAを作り、「1個だけ動かしてBを作ってね」と設問。こぐま会のドリルは回転させた時のイメージを促すもの。小学校受験などにもペーパーで出てきますね。
おすすめ無料アプリ:算数忍者

アプリで立体図形の問題をお探しならこにら。立体図形に関する問題が豊富なアプリ。平面に描かれた立体図形に慣れるのにもってこい。図形の数を数えたり、動かす問題を通して、3Dの感覚を育てます。
おすすめ図形遊び:書かれた積み木が何個か当てる
ちびむすドリル

こちらは、積み木の絵を見て何個でできているか当てる学習プリント。4歳くらいから年長さんまでの間に、簡単なものから少しずつ取り組んで頂きたいもの。

同じサイトの40個までの積み木を数えることも、年長さん後期~小学校低学年で挑戦してみましょう。
図形を苦手にさせないためにおもちゃやアプリを活用しよう
いかがでしたか?今回ご紹介した知育玩具や教材はあくまで一例です。年齢やステップも目標レベルなので、「うちの子全然追いついてない!」なんて焦らないでくださいね。重要なのは、8歳までにできるだけ多くの図形に触れること。お子さんのペースに合わせ、焦らず取り組んでください。無料のアプリやインターネット教材も上手に活用して、楽しみながら図形遊びを取り入れてみましょう!

前回記事:【年齢別・図形問題】図形が苦手な子どもにしない!学習前の鉄則
次回記事:子どもの言葉の発達はいつから?すぐできる!表現力を育てる0歳からの過ごし方
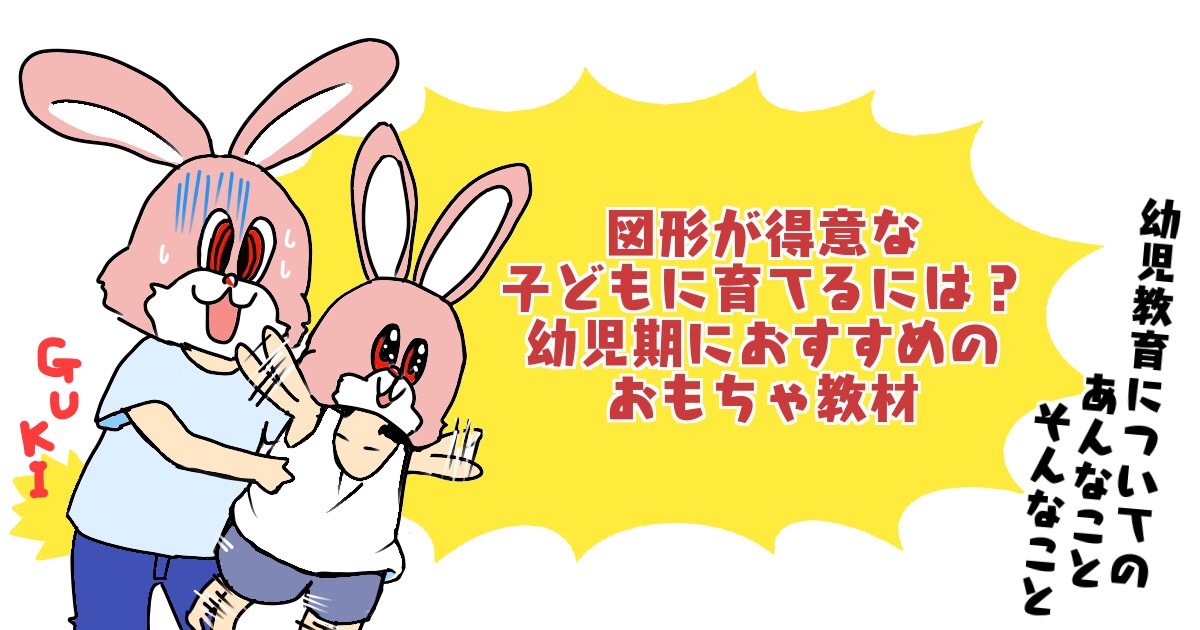

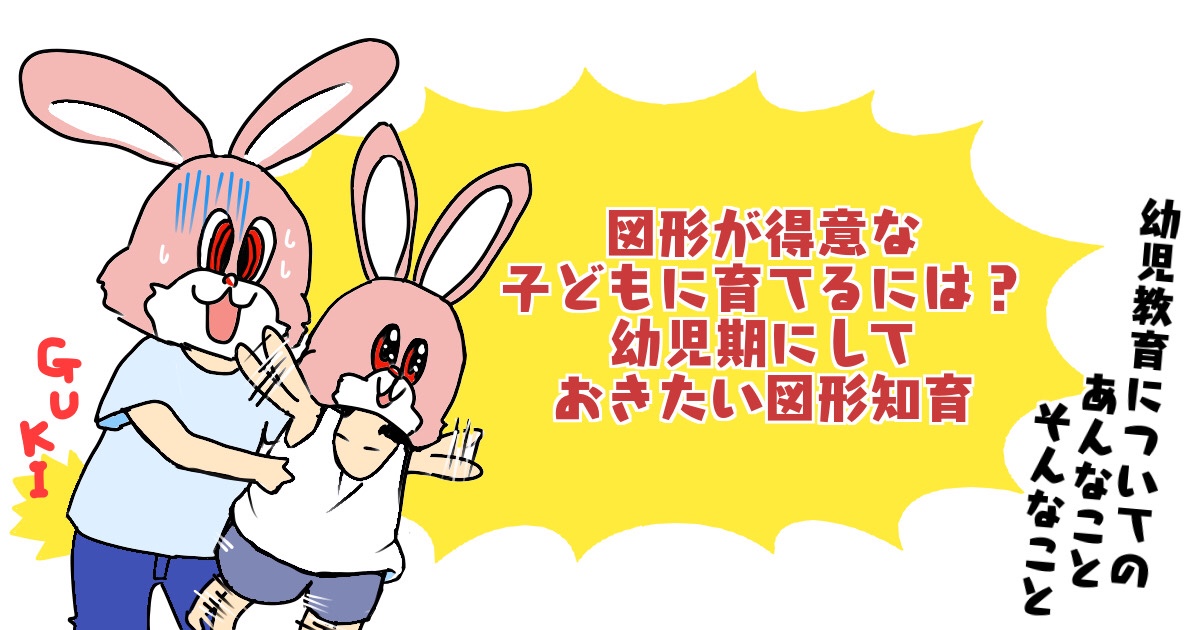
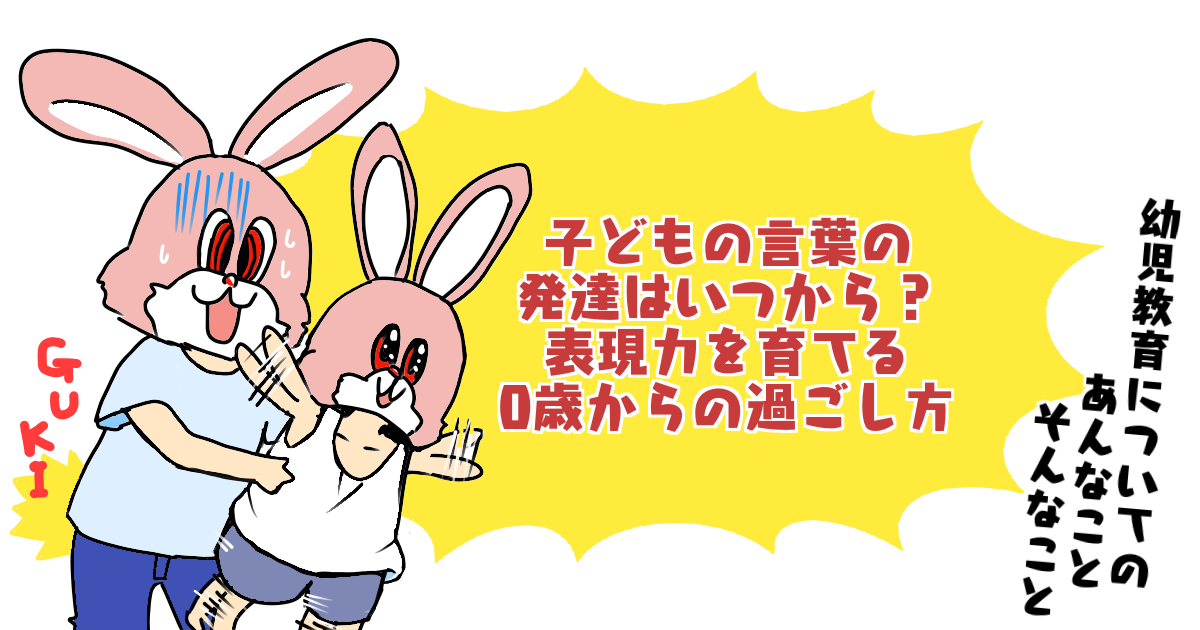
コメント