前回の記事では、幼児期における数の学習について、効果的な教え方や目標とするステップをご紹介しました。
参考:子どもを算数好きに!幼児期の教え方は?年齢別の取り組み
では、実際にどのようなおもちゃや教材を使えば、算数の基礎力やIQを伸ばせるのでしょうか?今回は、年齢別におすすめの知育玩具や無料ダウンロード教材をご紹介します。
Amazonの商品の他、インターネットで無料ダウンロードして使える教材を見ていきましょう。

3歳未満におすすめの算数教材【1つの物を1つと数える】
3歳の幼児教育では、まず「1対1の対応」ができるようにすることが重要です。指さししながら数を数え、少しずつ数の概念を身につけていきましょう。
ステップ1. 「1~5までのもの」を数える
おすすめ教材:百玉そろばん
-
指で玉を動かしながら数を数える練習に最適
-
色分けされているものを選ぶと、直感的に理解しやすい
-
まずは1列を使い、「5と5で10」などの基本的な数のインプットを行う
対象年齢:3歳~
3歳頃に必要なのは、100まで数唱できることよりも、10までの具体物を数えられること。百玉そろばんは、楽しく具体物を数えるのに適しています。3歳時点で100まで数える必要はないので、120も150も玉のあるそろばんよりも、色分けされて使いやすいものを選ぶのがベスト。
こちらは、幼児教室の多くで採用されている百玉そろばん。幼児がつまみやすく、動かしやすいサイズ。1~10まで数えたり、「5と5で10」のように、まずは一列を使って数のインプットをしていきましょう。
対象年齢:6歳~
「いやいや、もう少し安くてプラスαがあった方が良い!」という方はこちら。そろばんの上に数字をのせて、足し算引き算の練習もできる優れもの。もちろん、3歳児期には数字プレートはなくてOK。6歳以降も使える知育玩具です。
ステップ2. 「1と1の対応」ができる
おすすめ教材:すごろく
-
サイコロを振り、出た目の数だけ駒を進めることで数の対応関係を学べる
-
初めは3までのサイコロを使うと理解しやすい
-
通ったマスにおはじきを置くと、視覚的に学習しやすい
対象年齢:3歳~
1と1の対応は、1つのものを1つと認識できる能力であり、数を数えるために必要不可欠。これがうまくできていないと、3個のものを4と数えるなど、上手く数が数えられません。1と1の対応がしっかりできるようになる知育玩具といえば、すごろくです。すごろくは、1が出れば1つのマス目を移動、2が出れば2つ移動という、1と1の対応の基礎を作ります。
最初からコマをマスの分動かすのは難しいので、通ったマスに積み木やおはじきを置くのがおすすめ。サイコロで2が出たらおはじきを2個、次に3が出たら続きから3個置く…というように、コマ代わりにたくさんのおはじきを使う(通ったところすべてにおはじきが乗る状態)のが良いですね。サイコロも最初から6までのものは難しいので、3までのものを手作りしても良いでしょう。
ステップ3. 数の比較ができる
おすすめ教材:数の比較パズル
-
1~10の数を色分けしているため、直感的に多い・少ないが理解できる
-
「どちらが多い?」「どちらが少ない?」とクイズ形式で遊ぶと効果的
-
数の合成や差の学習にも活用可能
対象年齢:3歳~8歳
数だけでなく、図形のIQも伸ばせる知育玩具がこちら。特に、1~10で色分けがされているので、数の比較がしやすい数字パズルです。「紫とピンクどちらが多い?」「どちらが少ない?」といった形で、数の多少の当てっこ遊びを行いましょう。
少しお兄さんお姉さんになったら、数の合成や差を答える遊びにも使えます。さらに、パズル遊びを通して数字と量を一致させるのにもぴったりです。
年少3~4歳におすすめの算数教材【10までの数を確実に】
数を数えることができるようになったら、次は数の操作に取り組みましょう。足し算や引き算を意識しつつ、楽しく学べる教材を活用します。
ステップ1. 違うものであっても数の比較ができる
おすすめ教材:ちびむすドリル(無料)
-
数の比較や同数発見など、豊富な問題が無料ダウンロード可能
-
書くことが好きなら、数を書く練習にも活用できる
ちびむすドリル https://happylilac.net/kazu-ikututo.html
数の問題が多数取り揃うサイト。違う色や形のものでも「同じ数である」「数が違う」などの認識ができると、数の比較の能力はおおよそ完成したといえます。書くのが嫌いでなければ、挑戦してみましょう。
対象年齢:3歳~
くまや花、りんごなどが1~12まで描かれたカード。「同じ5個絵が描かれたものを集めよう」と同数発見遊びを通して、違うものでの数の比較ができます。その他、数の合成や差、多少など、この1セットでさまざまな数遊びが楽しめます。
ステップ2. 「10までの数の合成」ができる
おすすめ教材:動物の足で足し算カード
-
例:「4本足のカエルと2本足のツルの足は全部で何本?」
-
楽しく問題を解くうちに、自然と数の合成が身につく
対象年齢:3歳~
動物の足で足し算をマスターしようという斬新な知育玩具がこちら。カードにはそれぞれ、生き物の足の数をピックアップした絵が描かれています。
例えば、「4本足のカエルと2本足のツルの足は全部で何本?」といった具合に問題が出せます。前項の「違うものを数えて合成する」こともできる上、知能検査などにも登場する一般常識「動物の足の数」も学べます。
数の合成は、おはじきやシールでも簡単にできますが、子どもたちがハマるという点で、この商品は絶対おすすめです。
ステップ3. 「1~3くらいまでの数の差」が分かる
おすすめ教材:カエルの天秤おもちゃ
-
カエルの数を比べながら、数の差の概念を学ぶ
-
「何匹足りない?」と問いかけることで、不足・過不足の理解を深める
対象年齢:3~8歳
数の差は、子どもにとって難関。最初から数字で教えこむのは絶対避けましょう。こちらは、視覚的に数の和・差を学習できる知育玩具。
カエルはそれぞれ同じ重さなので、2匹と3匹を比べて「何匹多い?」というように声かけしてみてください。「何匹多い?」の聞き方が難しいようなら、少ない方を指して「何匹足りない?」と同数にするように促しましょう。「1匹足りなかったね、ということは、こっちが1匹多かったね。」というようにインプットすれば、差の概念が徐々に育っていきます。
また、このおもちゃは数字がそれぞれカエルの重さ分になっているため、数字と量の一致や数字の足し算引き算にも応用できます。
4~5歳におすすめの算数教材【加減乗除の数操作に触れる】
この時期には、数の操作を理解できるようになります。楽しく学ぶために、ゲームや遊びの要素を取り入れましょう。
ステップ1. サイコロを使って数の合成遊び
おすすめ教材:サイコロ足し算ゲーム
-
12までの数の合成ができればOK
-
2つのサイコロを使って、足し算の練習をする
-
慣れたら10面ダイスを使って20までの合成に挑戦
対象年齢:5歳~
サイコロで足し算、つまり12までの数の合成ができれば、年中さんとしては花丸です。もちろん、「6+6=」がすぐにできなくてもOK。サイコロの目と目を合わせて数えるのでも十分です。
すごろく2つを使って遊ぶ、知育玩具を用意するなど、やり方はさまざま。普通のサイコロすごろくに慣れたら、クモンの少し難易度高めのすごろくに挑戦してもGOOD。サイコロは数字の10面ダイスで、20までの合成の練習ができます。頭の中で足し算が難しいなら、おはじきなどを使いましょう。
ステップ2. 数の規則性を見つける
おすすめ教材:オリジナル問題プリント
-
例:「1 2 1 2 1 2 ○ 2」「1 1 3 1 1 ○ 1 1 3」
-
規則を見つけることで、論理的思考力も鍛えられる
-
印刷して繰り返し練習可能
市販のドリルではなかなか登場しないため、親御さんが問題を作って解いてもらうのが良いかもしれません。ただ、面倒なことだとおもうので、こちらでもご用意しました。
【PDF版】小学生用無料IQテスト公式問題集!自宅で正確な子供の知能診断ができる調べ方
タブレットで学ぶならこちら↓↓
【RISU算数きっず】でIQ上がる?自宅で算数力アップできる知育タブレットを幼児教室講師がお試し|タブレット比較検証
ステップ3. 等号・不等号の理解
おすすめ教材:学研の算数ドリル
-
「>」「=」「<」の記号を使った比較問題が充実
-
大きい数字、小さい数字の認識がしっかりできるようになる
対象年齢:5歳~
不等式を学ぶのは小学校中学年頃。ですが、同数発見や数の多少を習慣的に行ってきた子どもであれば、これらの理解は簡単です。例えば、大きい丸と小さい丸を描いて、大きい丸に大きい数字、小さい丸に小さい数字を書かせます。また、同じ大きさの丸には同じ数を入れるようにします。
これだけで、不等式(>の式)や等式(=の式)の基礎理解はクリア。より詳しくやるなら、ドリルを使ってもよいかもしれません。こちらの学研のドリルは、大きい数字も含めた同数発見や数の大小問題の宝庫。書くのが嫌いにならないようなら、挑戦してみましょう。
5~6歳におすすめの算数教材【さまざまな数の操作】
年長さんになると、より高度な計算やルールのあるゲームにも挑戦できます。
ステップ1. 「3つの数の合成」ができる
おすすめ教材:数字カードゲーム
-
2つ、3つの数の足し算をしながら得点を競う
-
遊びながら計算スピードが向上
対象年齢:6歳~
年長さんまで、数の問題にたくさん触れてきた子どもは、○+○+○などの3つの合成も上手にできるようになります。また、計算を取り入れたルールのあるゲーム遊びを取り入れるのも良いでしょう。
この知育玩具は、数字好きな子どもにぴったりなカードゲーム。数字が書いてあるカードを交互に裏返し、数字の和が10にできたら自分の得点になります。2つ、3つの数の足し算が必要なので、とても難しいゲームですが、楽しく何度も遊ぶことで、非常に計算の速い子どもになります。数字だけで計算するのが難しい場合は、おはじきなどを使うと良いでしょう。
ステップ2. 積み木を見て頭の中で数を数えられる
おすすめ教材:キッズステップ積み木問題
-
図形的思考力と数的思考力を同時に鍛える
-
奥行きのある積み木を目で数えることで、より高度な認識力を養う
図形的思考力と数的思考力を同時に発揮するのは、かなり難しい作業です。数、図形どちらも取り組んできた子どもであれば、年長さん頃にはすんなりできるようになっているはず。
上記のサイトでは、ステップ別に問題がプリントできるので、ぜひステップ1から挑戦してみましょう。奥行きのある積み木を、目で数えることまでできれば、それは数も図形も理解がしっかりできている証拠です。
ステップ3. 数の規則性を見つけられる
おすすめ教材:知育タブレット
-
自分のレベルに合わせて問題を進められる
-
小学校入学前の準備としても最適
-
月額制でコスパも良好
対象年齢:3歳~
年長さんになったし、さまざまな問題や数に触れる機会が欲しい…でも色々買うのは予算オーバー。そんなご家庭なら、キッズタブレットもおすすめです。時間を決めて取り組めるなら、自分のレベルに合わせてどんどん先に進め、小学校入学準備もできます。
Amazonの知育タブレットは、月額500~1,000円で数千点のキッズコンテンツが使い放題。「ベネッセこどもチャレンジ」の算数・国語問題を取り組めます。その他、英語や児童書、歴史漫画など、さまざまな学習コンテンツあり。1台で小学校卒業まで使用できることを考えると、かなりコストパフォーマンスが良いといえます。
幼児期の算数学習は「楽しく」がポイント!
数の概念を学ぶには、具体物で遊ぶことが一番!おもちゃや知育玩具を活用することで、子どもは自然と算数に親しみを持つようになります。
また、無料のプリント教材やアプリ、手作り教材も活用しながら、遊びの中で算数の楽しさを学ぶ機会を増やしていきましょう。
次回の記事では、小学生向けの知育玩具や家庭で楽しめるテーブルゲームをご紹介します!
いかがでしたか?
数の概念を楽しく学ぶためには、4歳頃まで具体物で遊ぶに限ります!
教室に来ているママさんで、おもちゃも知育玩具も、子どもに自作させているという兵【ツワモノ】もいらっしゃいました!

前回記事:子どもを算数好きに!幼児期の教え方のコツ5つ+年齢別数の取り組み12
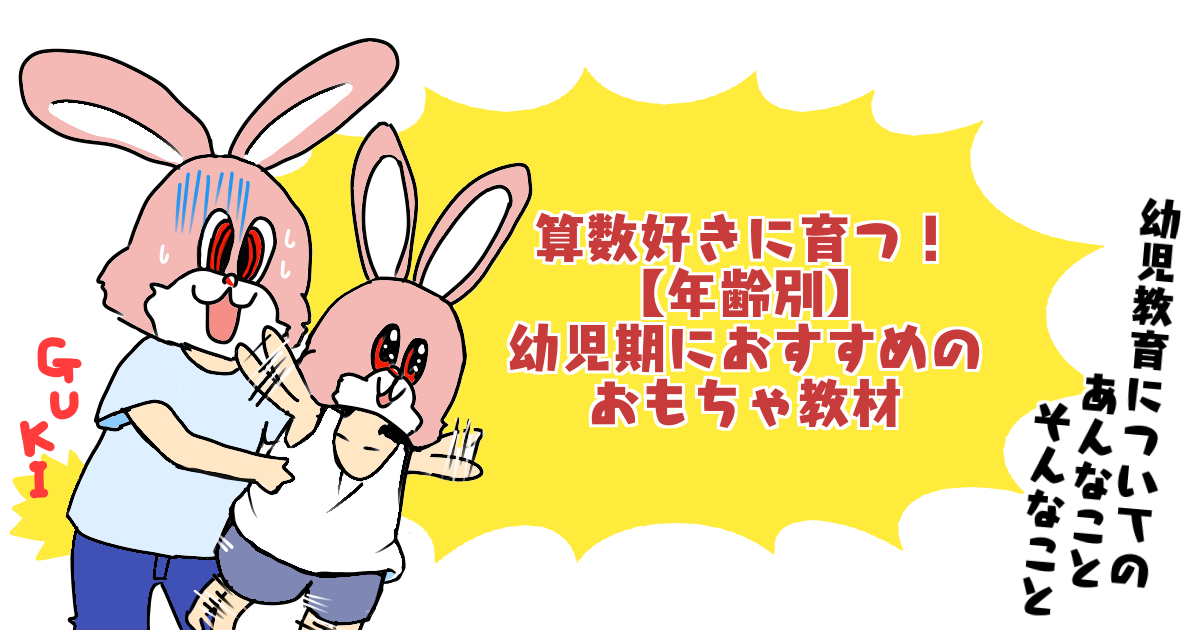


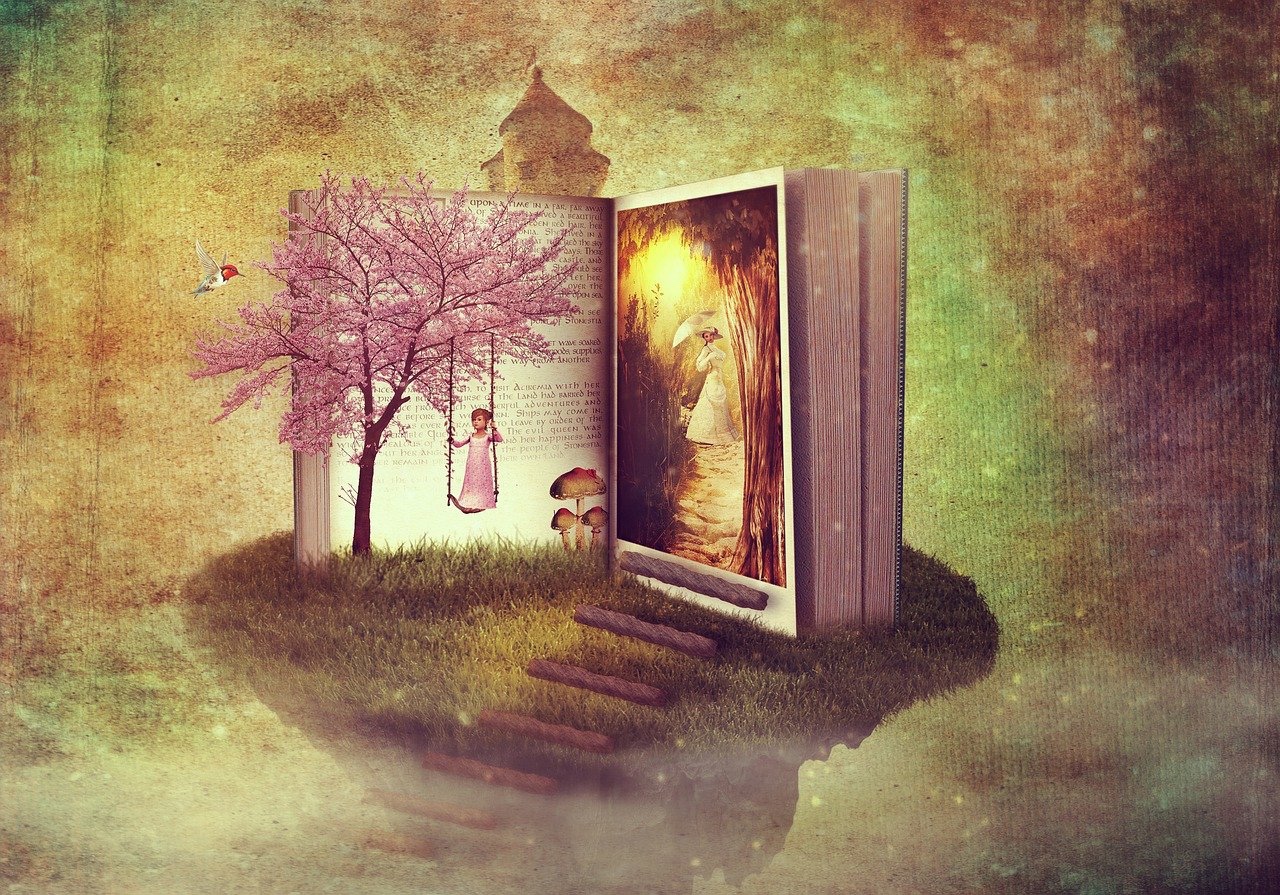
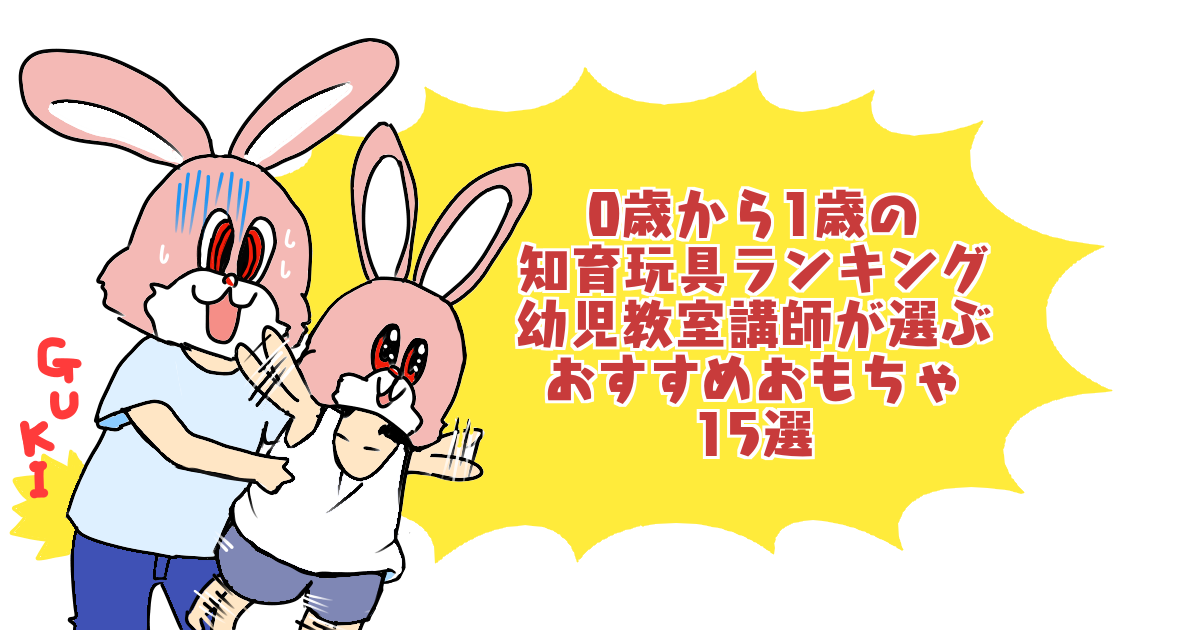
コメント