
最近、英語で昔の漫画を読んでるんですけど…。

いいですね。面白いですか?

はい。ただ、気になるのが、コマを左から右に読まなきゃいけないんですよね。

最近の日本の漫画の英語版は日本式で、右から左に読むものが多いですが、けっこう古い漫画なんですね。

はい…。左から右に読むために、なんと絵も反転してるんですよ!!!!

そんな想定してない絵を反転されるなんて、絵描きとしては恐ろしいことないんです!!

…今日は、なぜ日本語の縦書きは「右から左」なのか、横書きが「左から右」なのか、違いとその理由を見ていきましょうか。
漫画や台本、国語の教科書、新聞、文庫本は縦書きで、算数や英語、社会、理科の教科書が横書きであることを不思議に思ったことはありませんか?今回は、そんな縦書き(縦読み/縦文字)横書きの違いをご紹介。なぜ右から左に読む?横書きは左から右?右から左に読むのはいつまで?日本語をどっちから読むのか、順番について徹底解剖していきましょう!
日本語の縦書きは「右から左」、横書きは「左から右」
「日本語はなぜ右から左に読むのか?」「縦書きの文庫本、どっちから読むの?」こうした疑問は、語学学校でも外国人がよく持つものです。欧米をはじめ、多くの国々では文章は「左から右」に横書きされます。日本の場合は、縦書きと横書きが混在している状況です。
縦書き(右から左)横書き(左から右)2つの読み方がある
外国人向けの日本語教材は、主に「左から右」に横書きされています。学校の教科書も、国語以外の科目ではこの形式が主流です。一方、市販の本では、文庫本や漫画などの右綴じのものは縦書きで「右から左」に読み進めます。洋書や雑誌、啓発本など左綴じのものは「左から右」に横書きされています。
つまり、日本では「縦書きのときは右→左」、「横書きのときは左→右」と使い分けられており、私たちは無意識にその法則に従って読んでいるのです。

意識したことありませんでした…!
横書きで「右から左」に読む時代はいつまで?

「んどう」…?あ!「うどん」か!「ンラトスレ」??…「レストラン」か!
昔の看板や映像で、「ん?これ読めない?あ、読めた!」と感じたことはありませんか?これは、かつて横書きでも「右から左」に読まれていたためです。
上の写真は、とある駅のストリートギャラリーにあるものです。古い写真なので少し見づらいですが、中央にはちょっと不気味な看板があり、その隣には「スピルカ」(カルピスの広告看板)があります。
このように、昭和初期までは横書きでも「右から左」と「左から右」が混在していました。横書きでも、「どっちから読むの」と混乱しやすい時代もあったのです。

ちなみに、横書きの新聞見出しも、昭和初期まで「右から左」でした。

なぜそんなややこしいことが…

おや、時代と歴史がヒントになってますよ。勘の良い方はもうお分かりですね。
日本語はなぜ右から左?なぜ左から右もある?
さて、外国人が日本に来て驚くことの一つに、「なぜ日本語には『右から左』と『左から右』の両方の読み方があるのか?」という疑問があります。確かに、横書きで右から左に読むことは昭和以降なくなりましたが、漫画や新聞、国語の教科書など縦書きで右から左に読む文化はなくなっていません。その理由を探ってみましょう。
縦書きが「右から左」である理由
まず、縦書きが「右から左」になっている理由についてです。日本では、縦書きの際に文字を上から下へ、そして行を「右から左」に進めます。これについては、「どっちから読むっけ?」と思う人は少ないでしょう。長い歴史の中で、日本語は右から左に書く言語でした。
これは、漢文の書き方に倣ったもので、日本語の文字はすべて漢字やそれから派生したひらがな・カタカナで構成されています。これらの文字は、縦書きを前提とした筆順で作られており、日本語が縦書きで「右から左」に読むのは自然なことだといえます。
また、右→左に読むのは、巻物に書いていたからという説もあります。巻物に書くとき、右利きなら左手で巻かれている部分を持ち紙をずらしていたため、自然に「右から左」に進めていたのです。
横書きでも「右から左」がある理由
それでは、なぜ横書きでも「右から左」に読むものも存在していたのでしょうか?これは、漢文の縦書き「右から左」が、横書きでもそのまま採用されたためです。江戸時代の刊行物など横書きのものも「右から左」が主流でした。

もっとも、江戸時代には横書き自体が少なかったんですけどね。
ところが、明治時代に西欧文化を取り入れ始めると、横書きが増え「左から右」の書き方も広まっていきました。もし日本が西欧文化を取り入れていなければ、横書きでも「右から左」が主流だったかもしれません。

だから、明治から昭和初期の看板や広告に僕たちが読みにくいものがあるんですね!
横書きはなぜ「左から右」になったのか?
日本で横書きが「左から右」になった理由は、主に欧米の影響によるものです。欧米列強と並び立つため、またはその文化を積極的に取り入れたいという意識から、看板や広告の横書きも「左から右」が流行するようになりました。

横書きの「左→右」は、当時の一種のトレンドだったのかもしれませんね。
ちなみに、日本で「左から右」の横書きが見られるようになったのは、18世紀後半にオランダから蘭学を取り入れ始めたことがきっかけです。1788年に出版された『蘭学階梯』がこの形式を紹介し、民衆にも「左→右」の横書きが広まりました。
この形式が一般化したのは戦後で、1946年には新聞の見出しが「左から右」の横書きに、その後、紙幣や出版物も「左から右」の横書きに変わりました。現在では、官庁の文書ガイドライン『公用文作成の要領』でも、「書類の書き方について、なるべく広く『左横書き』を採用すること」が推奨されています。
本や漫画はどっちから読む?
日本語の本や漫画も、この「右から左」と「左から右」の順番について、歴史的な影響を大きく受けています。
一般書籍は横書き(左から右)
これまで見てきたように、書物はもともと縦書きが基本で、「右から左」の縦書きが読みやすい右開き・縦組みの本が一般的でした。左開き・横組みの本は、大正から昭和初期にかけて増加しました。

江戸時代にはオランダの本を真似て、タイトルだけ左→右の横書き、本文は右→左の縦書きなんていう例もありましたよ。
戦後、「左から右」の横書きが主流となり、アルファベットなどの横文字が普及する中で、書籍の横組みも急速に広がりました。こうして、左開き・横組み、右開き・縦組みの本が両方とも書店に並ぶようになったのです。
国語の教科書・文庫本は縦書き(右から左)
しかし、伝統的な日本語の文章の書き方を学ぶため国語の教科書が縦書きです。古典文学や詩歌、書簡など、歴史的な文献を読む際に縦書きが基本となるため、国語教育においても縦書きが標準的な形式として採用されています。これにより、学生たちは伝統的な日本語の読み書きを身につけることができます。
文庫本が縦書きであることも、日本の文学における伝統を重んじる文化の一環です。縦書きの文庫本は、右開きでページをめくるという日本独自の読書体験ができます。この形式は、視線が自然に縦に流れることを前提としており、リズムよく文章を読み進めることができます。また、縦書きは、詩や短歌など、情緒を重んじる日本文学の繊細さを引き立てる役割も果たします。
漫画の「右から左」が世界に広がる
日本は欧米を模倣して「左から右」を取り入れましたが、逆に日本の「右から左」の文化を世界に輸出しているものがあります。それが、漫画です。かつて、漫画が翻訳され欧米で販売される際には、絵を反転させて「左から右」に読ませるのが一般的でした。しかし、近年では日本のサブカルチャー人気や作者の意向から、「右から左」のコマの読み方がそのまま採用されています。
これは、ある漫画のドイツ語翻訳版です。欧米の本は左開きが一般的なので、左から1ページ目にどっちから読むのか注意書きがされています。「右から左に読む」と、コマの読み方が書かれています。

反転して欧米文化に合わせる→日本の漫画の読み方がある!にシフトしていったんですね。

僕が読んでる『うる星やつら』は反転されていましたが、留学中見つけた『犬夜叉』は日本の通りでした。

同じ作者でもそんなことが起こりますか。面白いですね。

でも、高橋留美子先生はさすがで、反転されてても違和感なかったんですよ。もし僕の描いた絵が勝手に反転されたら発狂するけど。
日本語の縦書き・横書きの順番に歴史あり!
いかがでしたか?外国人の何気ない疑問を調べてみると、そこには非常に興味深い歴史が隠れていることが分かります。私たちにとって当たり前のことでも、外国人の視点から見ると、新たな発見があるものです。
日本は、アジアや欧米から様々な文化を吸収しつつ、独自の文化を守り続けてきた国です。日常に溶け込んでいる文化も、意外と他国の影響を受けているのかもしれません。だからこそ、文化と歴史の勉強は面白いですね!
前回記事:日本語にはなぜ主語がない?主語・目的語を省略する3つの理由
次回記事:日本語なぜ「イギリス」?なぜアメリカが漢字一文字で「米」?
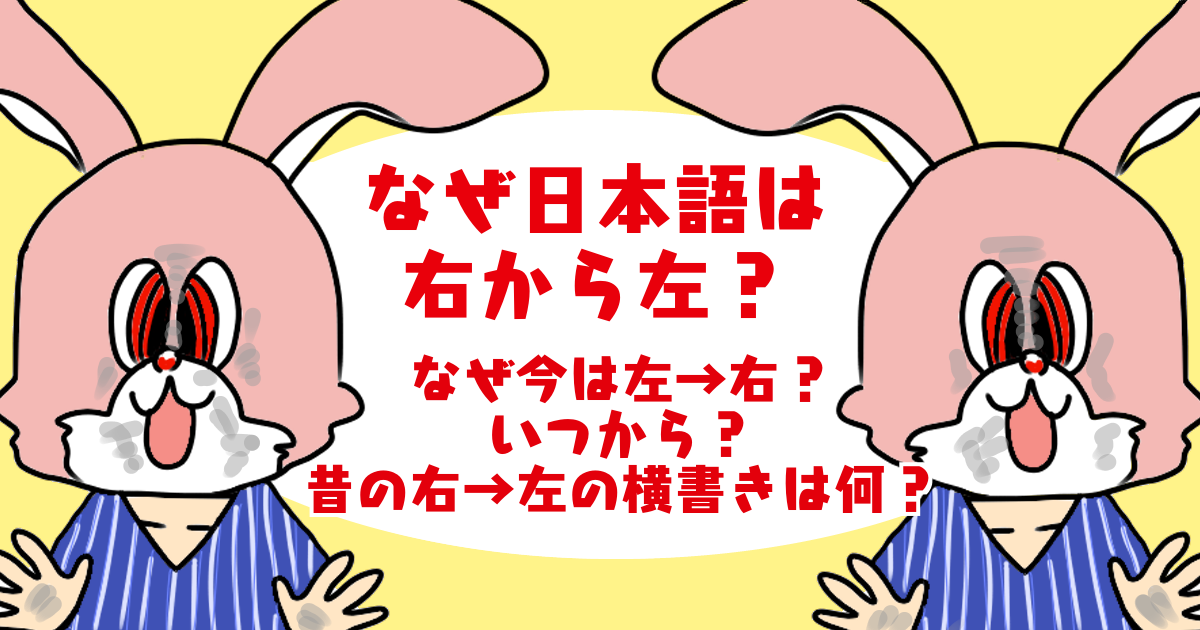



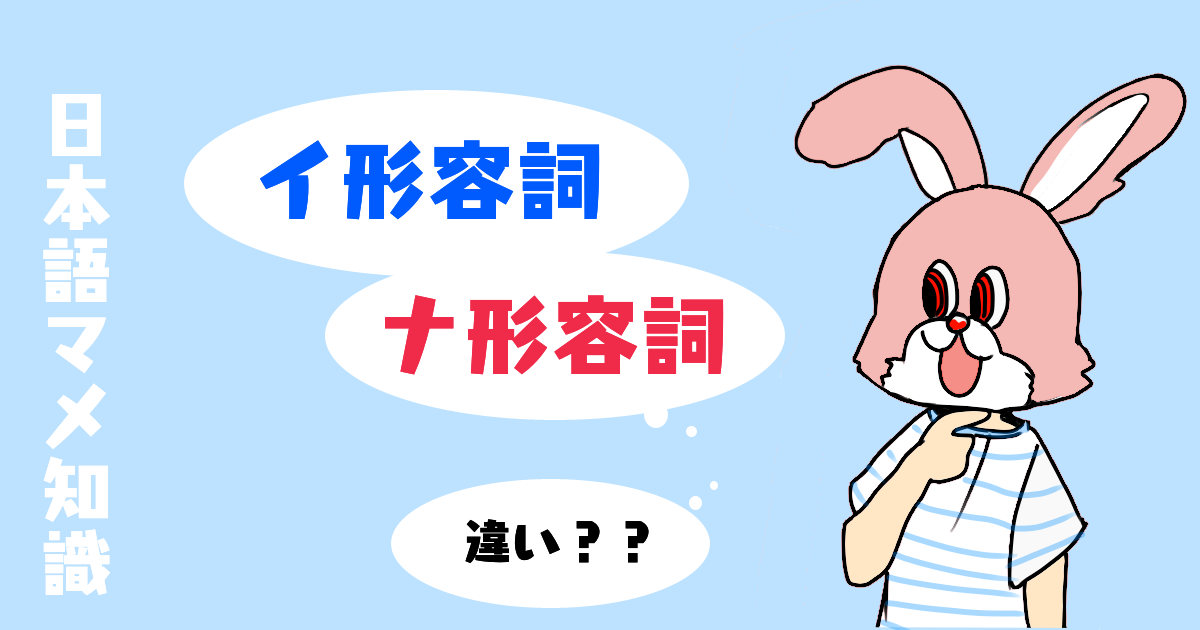
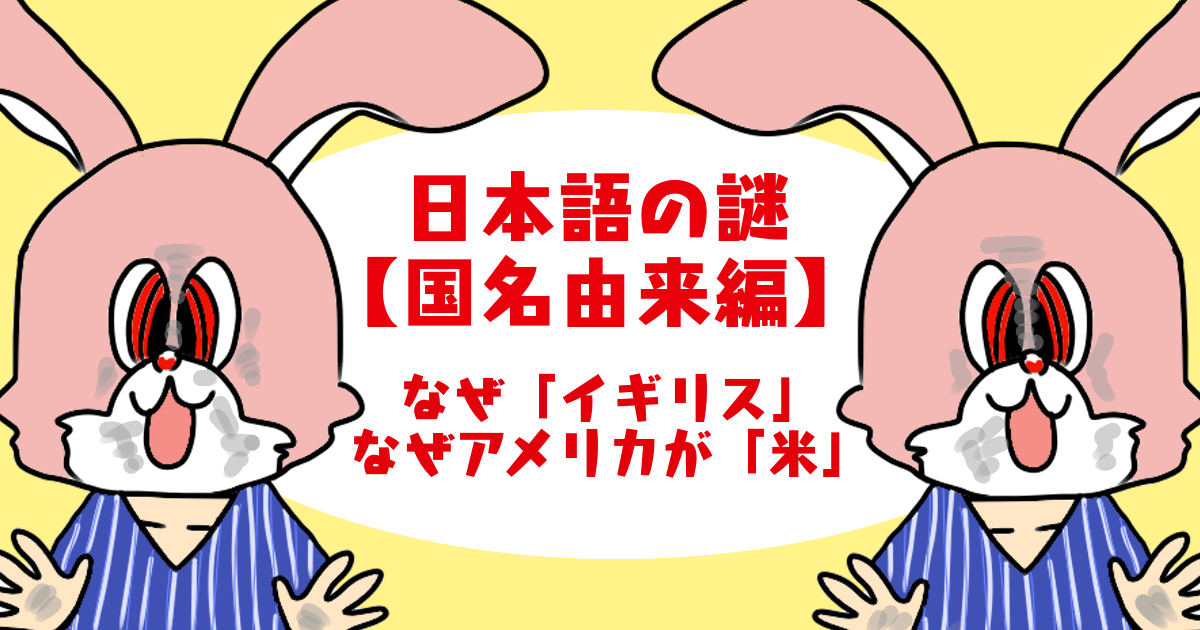
コメント