
うわっ、先生の机散らかってますね!お菓子の袋とか置いてる…ゴミ箱に捨てましょうよ! The teacher’s desk is such a mess! There are snack wrappers everywhere… You should throw them in the trash!

いえいえ、それは置かれているんじゃないんです!置いてあるんですよ! No, no, they aren’t just placed there. They were intentionally put there!

……同じじゃないですか…。…Isn’t that the same?

いやいや、「ている」と「てある」は全然違います。ちなみに、「ておく」も違いますからね。Not at all! “Te-iru” and “te-aru” are completely different. And by the way, “te-oku” is different too.

(話をそらした…。)(He changed the subject…)
「~ている」「~てある」「~ておく」は、どれも動詞と一緒に使い、物事の状態を表す文法表現。海外の学生は主に「みんなの日本語」29・30課で、「げんき」の15・21課などで詳しく勉強します。“Te-iru,” “te-aru,” and “te-oku” are grammar forms used with verbs to show different states or conditions. Many international students study them in Minna no Nihongo Lessons 29–30 or Genki Lessons 15 and 21.
これらの日本語文法の違いや区別はどんなところにあるのでしょうか。自動詞や他動詞、どちらを使うのでしょうか。ここでは、文法用法を英語付きでわかりやすく解説。例文や練習問題も見ていきましょう。So what are the differences between these forms? When do we use transitive or intransitive verbs? Here, we explain the grammar clearly with English support, along with example sentences and practice questions.
日本語文法:自動詞と他動詞とは
「ている」「てある」「ておく」の違いの前に、まずは、日本語文法における自動詞と他動詞を復習しましょう。「開く/開ける」「閉まる/閉める」など、日本語の動詞には同じ意味でも自動詞と他動詞でセットになる2つの言葉がだいたいあります。Before looking at the differences among te-iru, te-aru, and te-oku, let’s review Japanese intransitive and transitive verbs. In Japanese, many verbs come in pairs with similar meanings, such as aku/akeru (“open”) and shimaru/shimeru (“close”).
自動詞じどうし(intransitive verb)とは
- 自動で自然にそうなるとき使う動詞。Intransitive verbs are used when something happens naturally or on its own.
- 「ドアが開く。」「ドアが閉まる。」など
他動詞たどうし(transitive verb)とは
- 「目的語〜を」と一緒に使う人や生き物の動きを表す動詞。Transitive verbs describe the actions of a person or living being and are used with an object marked by o.
- 「ドアを開ける。」「ドアを閉める。」など
自動詞・他動詞の練習問題
②テレビを(つく・つける)。
③かばんに本を(入る・入れる)。
④散歩に行きたい犬が外に(出る・出す)。
⑤ガラスが(割れる・割る)。
⑥風で木の枝が(折れる・折る)。
⑦紙を(破れる・破る)。
⑧地震で家が(壊れる・壊す)。
⑨バス停にバスが(止まる・止める)。
⑩クリスマスが終わって飾りを(とる・とれる)。

『みんなの日本語』29課までの単語から出題しています。The questions here use vocabulary up to Lesson 29 of Minna no Nihongo.
「ている・てある・ておく」文法用法と例文
状態を表す「~ている」「~てある」「~ておく」は、文法上の使い方が決まっていて明確な区別があります。それぞれの用法と例文を見ていきましょう。The state-expressing forms te-iru, te-aru, and te-oku each have fixed grammatical uses with clear differences. Let’s look at how each one works, along with example sentences.
「~ている」の文法用法・例文
- 「動詞(自動詞)+ている」で「~の結果の状態」を表す。Formed with intransitive verbs + te-iru, it shows the resulting state of an action.
- 意図的でも意図的でなくても使える。It can be intentional or unintentional.
- その時だけその状態になったとき使う。It is used when something is in that state at that moment.
カバンが開いている。(そのときだけ)The bag is open. (only at that moment)
服が汚れている。(意図的でない)The clothes are dirty. (unintentional)
「~てある」の文法用法・例文
- 「動詞(他動詞)+てある」で「~の結果の状態」を表す。Using transitive verbs + te-aru expresses the resulting state of an intentional action.
- 意図的な行動の結果を表す。It shows the resulting on purpose.
- いつもその状態にあるとき使う。It is used when something is kept in that state.
コロナ対策のため、ドアが開けてある。(いつもその状態)To prevent COVID, the door is kept open.
塩は棚に入れてある。(意図的)The salt is stored in the cupboard.” (intentional)
「~ておく」の文法用法・例文
- 「動詞(意志動詞)+ておく」で「次の動作のために~した状態(準備)」「いつも通りの状態(通常)」「そのままおいた状態(放置)」を表す。Using volitional verbs + te-oku expresses a state created for a future action (preparation), as a regular routine, or left as it is.
- 話し手の意図的な行動を表す。It shows the speaker’s intentional action.
- 結果や目的が明確な時に使う。Used with a clear purpose.
- 「~とく」と省略できる。 It can be shortened to –toku.
母が誕生日なので、ケーキを買っておく。(準備)Since it’s my mother’s birthday, I’ll buy a cake in advance. (preparation)
パーティーの後、皿を洗っておく。(通常)After the party, I’ll wash the dishes. (routine)
すぐ逃げられるように、ドアを開けておく。(放置)I’ll leave the door open so I can escape quickly. (left as is)

「おく」は形式動詞で、補助的な役割です。「奥に置いておく」なんて言うと外国人は混乱してしまいますね。“Oku” here is a functional verb with an auxiliary role, so saying something like “place it in the back and oku” can really confuse learners.
「ている・てある・ておく」の違いと文法区別
ここまでで、「~ている」「~てある」「~ておく」、それぞれ用法と表す意味に違いがあることに気付かれたでしょう。それでは、さらに詳しく例文を交えて、「~ている」「~てある」「~ておく」の違いを見ていきましょう。By now, you’ve probably noticed that te-iru, te-aru, and te-oku each have their own specific meanings and uses. Let’s take a closer look at the differences between them with more detailed examples.
例文でくわしく「ている・てある・ておく」の違い
①手紙がAさんに届いている。
②手紙をAさんに届けてある。
③手紙をAさんに届けておく。
③ビールが置かれている(置いている)。
④ビールが置いてある。
⑤ビールを置いておく。
「置く」は、通常は「(目的語)を置く」という形の他動詞です。しかし、(特に会話の中では)主語や目的格によって自動詞として使われることもあります。上の例文の場合、③は自動詞、④と⑤は他動詞として使われています。“Oku” is normally a transitive verb used as “(object) + o + oku.” However, especially in conversation, it can also function like an intransitive verb depending on the subject or context. In the examples above, sentence ③ uses it intransitively, while ④ and ⑤ use it transitively.
③は、ビールはたまたまそこにあることを意味しています。④は、ビールが誰かの手によってずっとその場にあるという意味。放置されただけかもしれないし、飲むつもりで置かれただけかもしれませんが、いずれにしろ誰かの意図と理由が存在します。⑤も、意図的であり、理由が存在しますが、さらに「準備のために置いた」「いつも通り置いた」「放置した」というニュアンスが入ります。In ③, the beer just happens to be there by chance. In ④, the beer is there because someone intentionally placed it, and it has remained there. It may have been left there or placed to drink later, but in any case, there is someone’s intention and reason behind it.
In ⑤, it is also intentional and purposeful, but with an added nuance such as “placed as preparation,” “placed as usual,” or “left as it is.”
その他の文法用法「~ている」との違い

先生、「勉強している・食べている・飲んでいる」の動詞は他動詞ですよね?違うんですか?Teacher, the verbs in “studying,” “eating,” and “drinking” use te-iru, so they’re transitive verbs, right? Are they different?

いいところに気付きましたね。「~ている」には色々な意味があり、他動詞を使うときもあります。Great question. Te-iru has several meanings, and it can certainly be used with transitive verbs.
「今、ご飯を食べている。(進行形)」「毎日働いている。(繰り返し・習慣)」「結婚している。(状態)」「彼は大学を出ている。(経験)」など、「ている」の形には様々な意味があります。
For example: “I’m eating now.” (progressive) / “I work every day.” (habit) / “I’m married.” (state) / “He graduated from university.” (experience). The te-iru form expresses many different meanings.
上記で紹介した状態の「~ている」は「自動詞+ている」ですが、その他の文法用法では「他動詞+ている」を使うことも多くあります。実は、これらを混同して使ってしまう人が、日本人にもたくさんいます。The state meaning of te-iru is typically intransitive verb + te-iru, but in other uses, transitive verb + te-iru is also common. In fact, many native speakers mix these up.
①車が止まっている。(自動詞文)
②車を止めている。(他動詞文)
①は、車がそのとき止まった状態であることを指しています。②は、車を運転する人の動作の進行形で状態の継続を意味しています。In ① “The car is stopped.” (intransitive), the car is simply in a stopped state at that moment. In ② “He is stopping the car.” (transitive, ongoing action), the driver’s action is ongoing, expressing a continued action.
「ている・てある・ておく」 の練習問題
「~てある」「~ている」の使い分けを紹介してきました。「~てある」「~ている」の用法は、なかなかややこしく、日本人でも区別なく使っている人も多いものです。We have looked at how to distinguish between -te aru and -te iru. Their uses can be quite tricky, and even many native Japanese speakers often use them without making a clear distinction.

ここからは練習問題!( )の中に、「てある」か「ている」「ておく」を入れましょう。Now, let’s try some practice exercises! Fill in the blanks with -te aru, -te iru, or -te oku.
①エアコンをつけるから、窓は開け( )。
②図書館は、19時まで開い( )。
③道路に財布が落ち( )。
④聖書には、キリストの生い立ちが書い( )。
⑤「あれ、あなたの服、少し汚れ( )よ。」
まとめ
- 「~ている」は、そのときだけ「そのままの状態である」と言う意味。自動詞に接続。
- 「~てある」は、長い期間「そのままの状態である」という意味。他動詞に接続。
- 「~ておく」は、「あらかじめ~している(準備)」「いつも通り(通常)」「そのままの状態である(放置)」の意味。
前回記事:「~(する)ために」と「~(する)ように」の違いとは?
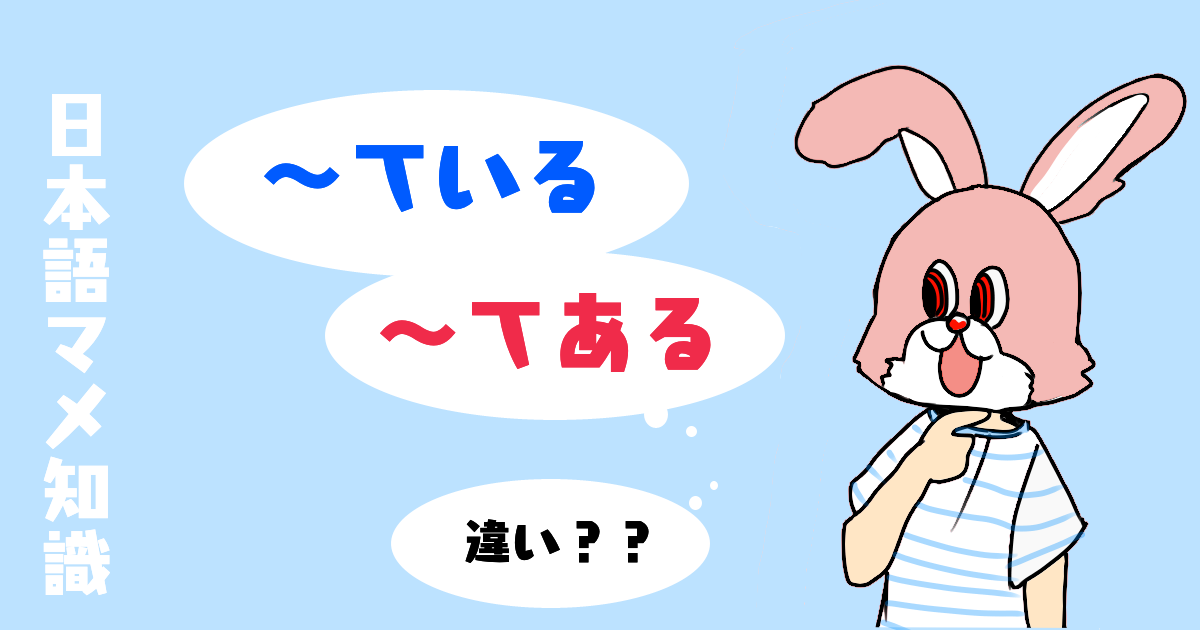

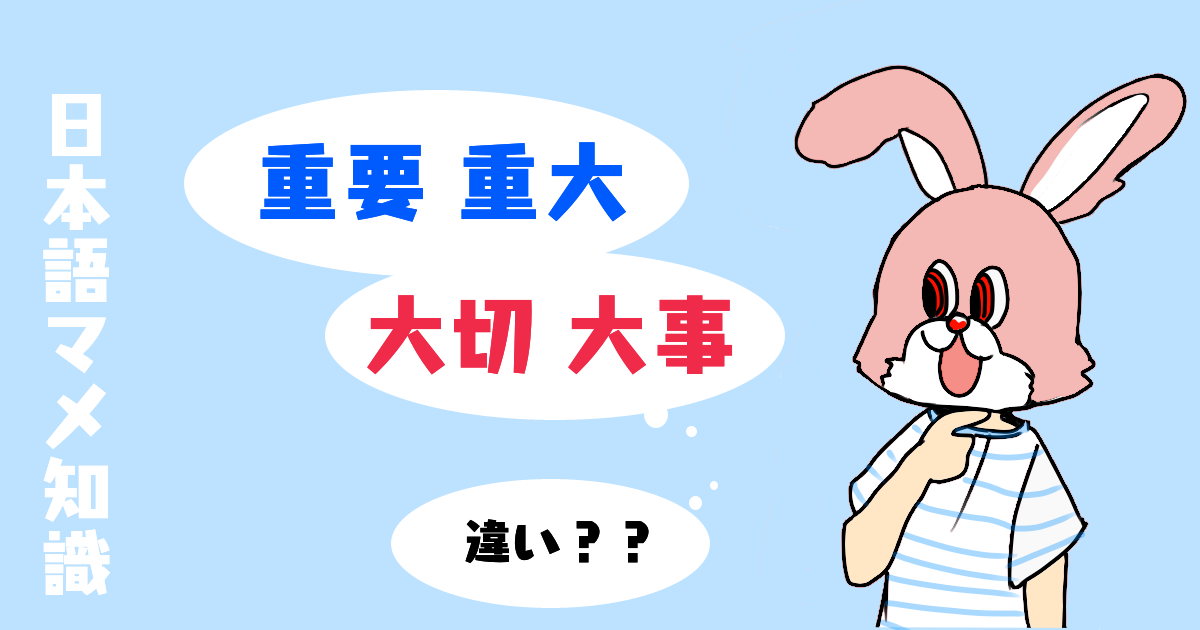
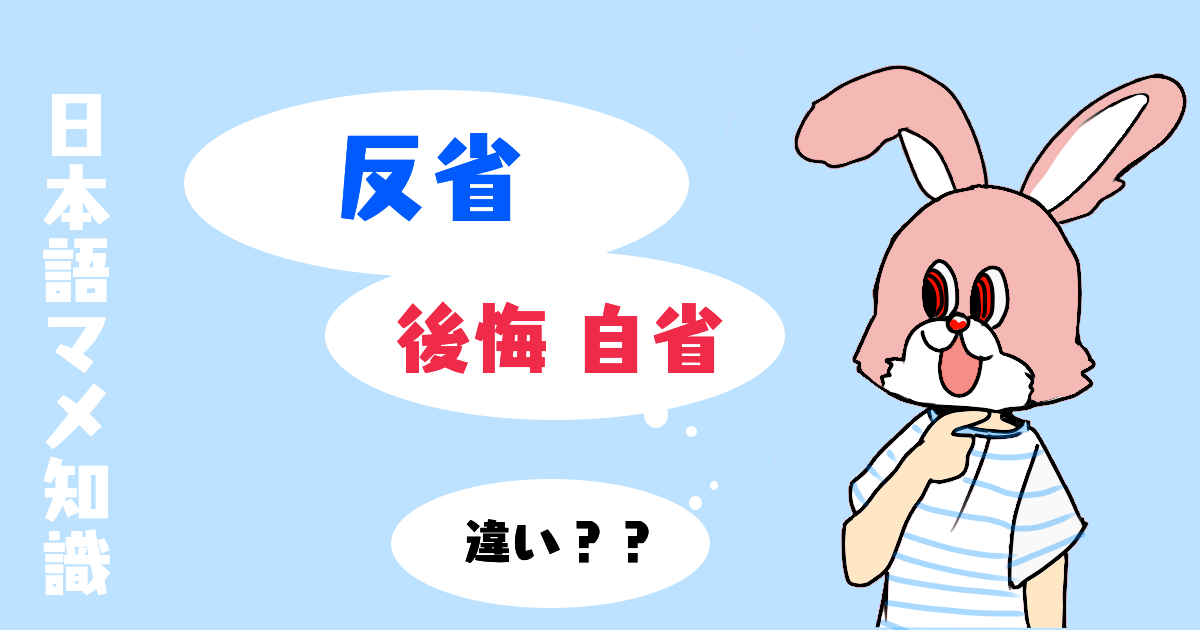
コメント
大変勉強になりました。ありがとうございました。
よかったです!コメントありがとうございました!