







【認識】【認知】はどちらも【理解】や【認める/解釈する】という意味。ですが、使い方に明らかな違いがあります。
認識と認知の違いとは
【認識】【認知】ともに「認める」という漢字が入る二字熟語。
難しい言葉なので、外国人なら中上級者向けです。
【認識】の意味・英語・類義語
認識とは、ある事柄をはっきり認めること。
その本質を理解すること。解釈すること。
英語:recognition(recognize/認識する), congnition
類義語:察知、知覚、感知、識別など
「売上向上は、広告効果によるものと認識しています。」
「この手続きを行うという認識でよろしいでしょうか。」
「認識の相違がないよう改めて確認する。」
【認知】の意味・英語・類義語
認知も同じく、ある事柄を認めること。
認識した上で、論理的に知ること。
英語:recognition, cognition, acknowledgement
類義語:理解、了知など
心理学では、知覚してそれが何か判断すること。
「彼はテレビを通して認知されるようになった。」
「その父親は自分の子どもであることを認知した。」
認識と認知の違い・使い分け
「彼を認識した。」
「彼を認知した。」
2つは字面がかなり似ていますが、 【認める】範囲に差があり ます。
「彼を認識した」なら、彼の本質を理解したということ。
「彼を認知した」なら、彼の存在を認めたということ。
この例の場合、【認知】の方がより知覚的で物質的な意味合いを持ちます。
感覚・知覚と認知の違いとは
【認知】とともに、心理学や医療でよく使われる言葉に【感覚】【知覚】があります。それぞれどのような意味でしょうか。
【感覚】の意味・英語・類義語
【感覚】とは、外からの刺激を感じ受けること、または内から受ける感情
視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などが代表的
英語:feeling, sense, impression
類義語:感受性、感性、感度など
心理学的には、「適応刺激を感受する過程」
「彼は感覚が鋭い。」
「方向感覚が良くない。」
「足元が崩れるような感覚に陥る。」
【知覚】の意味・英語・類義語
【知覚】とは、外からの刺激を感覚として捉えること。
英語:perception, sensation
類義語:感受、感知、智覚など
心理学では、感覚情報を取捨選択して情報伝達すること。
「犬とヒトの知覚を比べる実験。」
「知覚した情報は脳に送られる。」
「知覚過敏症を疑われる。」
感覚 知覚と認知の違い・使い分け
つまり、「皮膚で感じ取った刺激の情報が脳で判断される。」ということ。
こんな文章の場合、【感覚】【知覚】【認知】の違いが分かりやすくなります。
外からの刺激がある場合、まず【感覚】が【知覚】され、【認知】される。
【感覚】【知覚】【認知】の違いとは、【感覚】→【知覚】→【認知】という、情報伝達の順番の違いです。

認識と類義語 意識の違いとは
【認識】と字面が似ている日本語に【意識】もあります。
【意識】の意味・英語・類義語
ある事柄に気づくこと。
ある事柄や人を気にかけること。
「意識がはっきりしないほど酔っ払う。」
「目標を意識すると、モチベーション高く臨める。」
認識と意識の違い・使い分け
先程の例でいうと、「彼を意識した」というと、彼を気にかけること。
彼の本質を理解したという意味の「彼を認識した」とは異なります。
【意識】は、本質の理解を伴わなくても使用される言葉です。
ビジネスにおける【認識】の使い方
ビジネスシーンで【認識】という言葉はよく使われます。
自分の認識について、解釈が正しいかどうか、確認する場面で使用することが多いです。しかし、相手の認識については使うのは、不躾な印象を持たれます。
×「あなたは、~と認識していますか?」
ただし、接頭に「ご」を付けて「ご認識」と言えば、使われることもあります。
「~と、ご認識頂ければ幸いです。」
相手によっては、命令のように感じることもあるので、ビジネスシーンでは避けるのが無難でしょうね。
マーケティングにおける【認知】とは
マーケティングにおける認知とは、潜在顧客が商品やサービスを知る段階を言います。つまり、消費者の購買行動における第一歩。
企業が「まず消費者に商品やサービスの存在を知ってもらおう!」というときによく使う言葉です。 特に、一般的に知られていない商品や新たなサービスのマーケティング施策では、いかに潜在顧客に認知を促せるかが重要でしょう。
心理学における【認知】とは
心理学における認知とは、ものを知ることに関わる全ての機能のこと。つまり、外界の状況を知る知覚、経験したことがらを覚えておく記憶、理解と解釈の思考を言います。
そしてこれらを研究対象とするのが、認知心理学です。認知心理学では、人間を情報処理システムと見なして研究・分析が行われます。
類義語の感覚は、心理学的には適応刺激を感受する過程。知覚は、感覚情報を取捨選択して情報伝達することです。
まとめ
- 【認識】と【認知】の違い
【認識】とは、解釈し理解すること。
ビジネスで自分の認識について、解釈が正しいかどうか、確認する場面で使われる。
【認知】とは、知覚して認めること。論理的に理解すること。
マーケティングにおける認知は、潜在顧客が商品やサービスを知る段階。
心理学における認知は、ものを知ることに関わる全ての機能。
- 【感覚】と【知覚】【認知】の違い
【感覚】→【知覚】→【認知】の順に情報が伝達される。
- 【認識】と【意識】の違い
【意識】とは、気にかけること。【認識】と異なり、本質を理解していなくても使われる。
次回記事:【論理】【理論】【倫理】の違いとは?
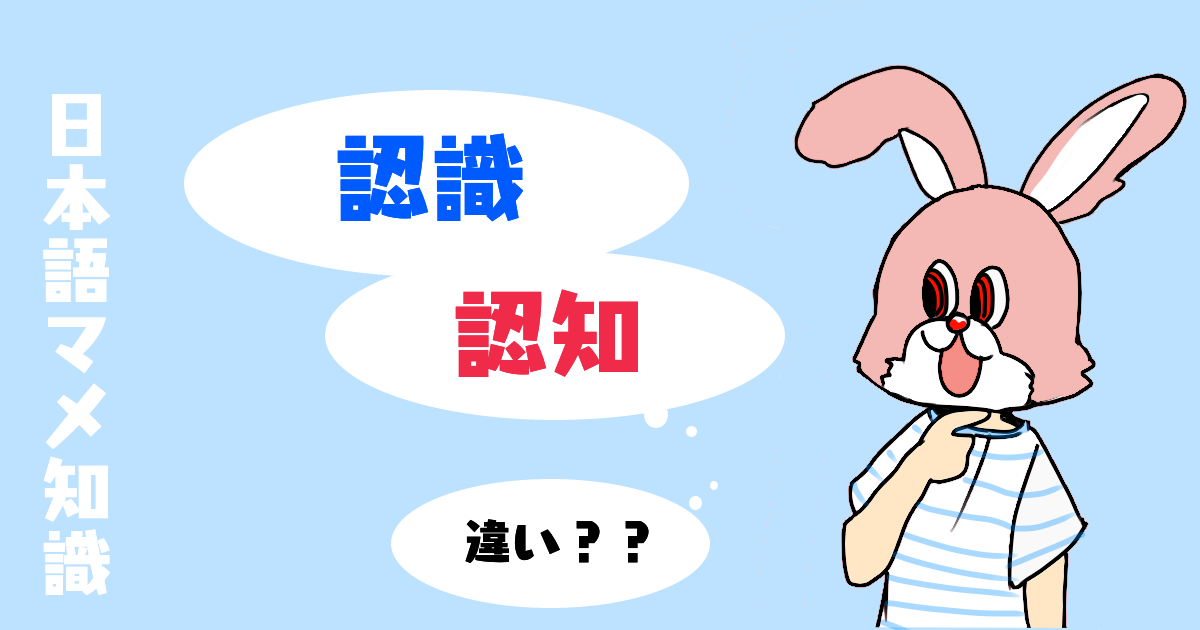

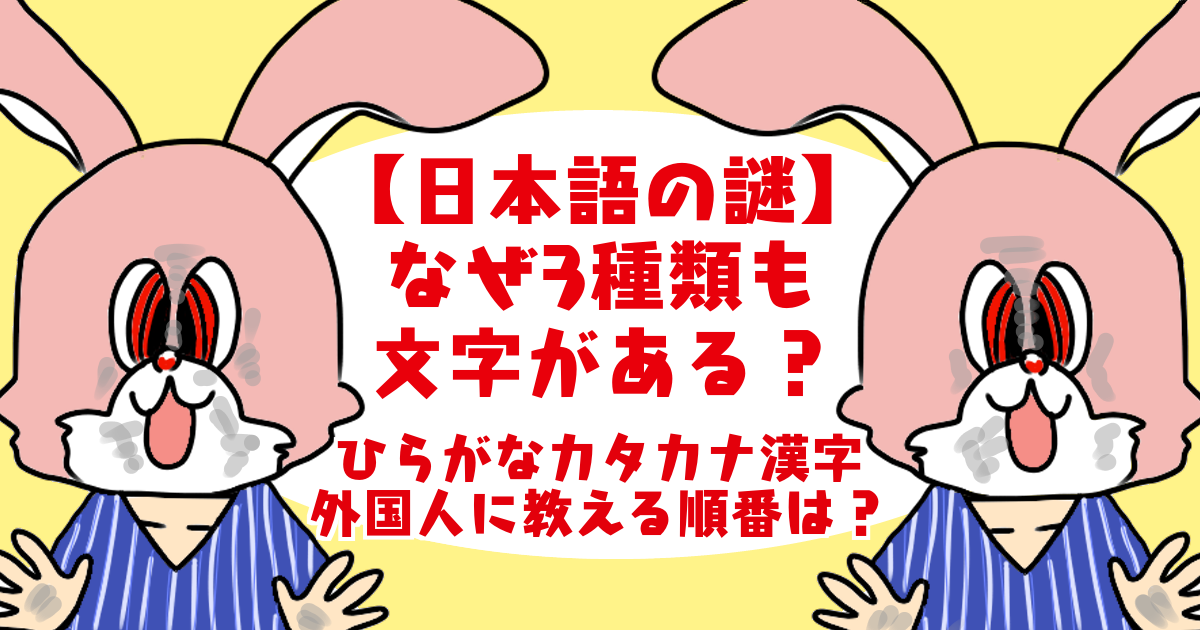
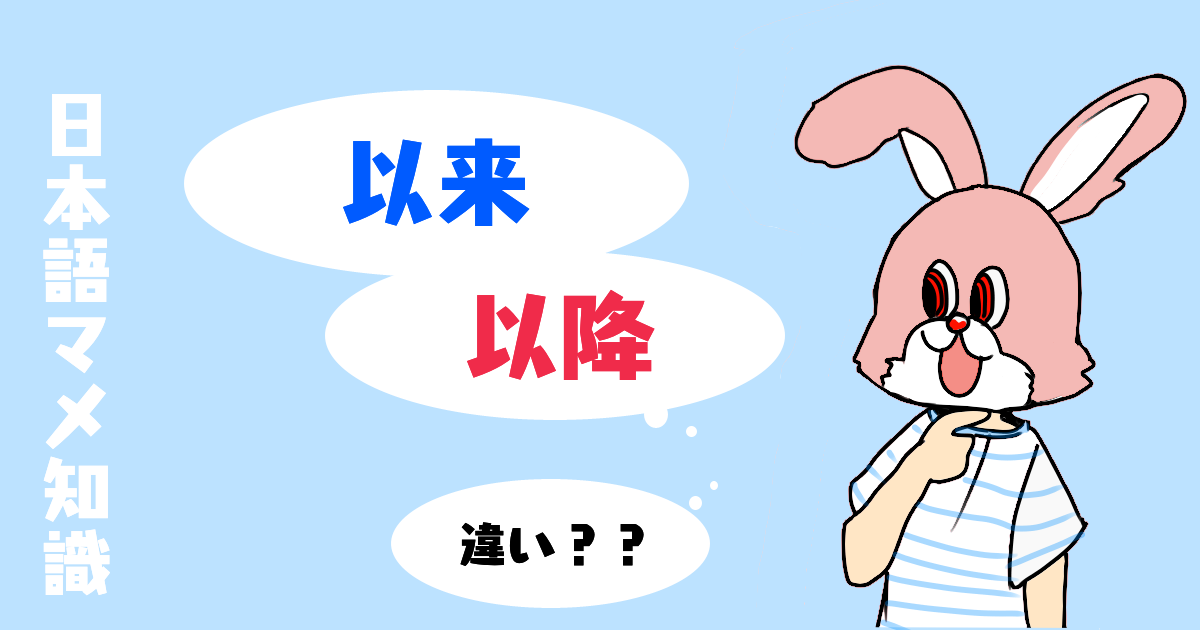
コメント