




ドイツ語と日本語の文法・発音は似てる?
ドイツ語は、英語と同じく西ゲルマン語派に所属するヨーロッパ言語。ゲルマン人の大移動で有名な、ゲルマン民族の話すゲルマン語を最も色濃く残した言語といわれています。
主にドイツ、オーストリア、スイスの一部、リヒテンシュタインなどで話される言葉です。
英語と同じくSVOを基本とする構文。英語との共通点も多いため、ドイツ語話者にとっては英語は簡単とされています。
ラテン系の言語に比べて発音の響きが重厚で、「かっこいい」「いかつい」「こわい」などの印象を持たれることがあるようです。
日本語とドイツ語の似てるとこ!共通点・発音が似ている言葉
ドイツ語と日本語は実は似てるんです!

ドイツ語は、SVO構文の言葉には珍しく、語順に制約が少ないのが特徴的。語順で気にすべきは動詞の位置くらいなので、語順に関わらない日本語と共通点がありますね。
また、発音は一部を除いてハッキリしていて、日本語話者でも発音しやすい言語といえます。
その他、完全に偶然で、同じ意味として使われる日本語と同じ発音のドイツ語も存在します↓↓
Ach so/あっそう
あいづちをうつとき、ドイツ人は頻繁に「アッソー」と言います。日本語の「あっそ」は少し不躾な印象ですが、ドイツ語では中立的なあいづちの言葉です。
Nanu!?/なぬ⁉︎
驚いた時、ドイツ人は「ナヌ!?」と言うこともあります。日本人ではそんなに多くないでしょうか?

日本語になったドイツ語に由来する言葉【医療】
明治の開国後、外国の文化やモノ・人がたくさん入ってきた時代、他の外来語と同じく、ドイツ語もたくさん入ってきました。
近代化のお手本としてドイツ帝国に習ったため、 社会・学問・政治・軍などドイツ文化の影響 が見られます。特に、医学用語や法律用語などは、ドイツ語由来の借用語・翻訳借用が多く存在し、ドイツ語から日本語になった外来語の多さの所以と言えます。
その他、この時代は学問や政治に関する翻訳語も多く生まれました。
Kart/カルテ
お医者さんが記入するカルテがドイツ語から日本語になった言葉と言うのは、有名な話。ドイツ語では「カード」という意味です。医療現場関係なく、「ポストカルテ」「クレジットカルテ」などにも使われます。

Röntgen/レントゲン
ドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンが発明し、その名がつけられたX線。これも、ドイツ語由来の外来語です。多くの国で、レントゲンと呼ばれています。
Allergie/アレルギー
日本では英語発音ではなく、「アレルギー」とドイツ語発音で言いますね。これは、「アレルギー」がドイツ語由来の言葉でだから。この言葉は1906年に考案され、その後、日本に入ってきました。語源は、ギリシア語の「allos/他の」+「ergon/働き」。
Virus/ヴィルス
日本では「ウイルス」ですが、英語由来でなく、ドイツ語由来の言葉です。


日本語になったドイツ語に由来する言葉【登山・スキー】
登山用語やスキー用語も、ドイツ語から日本語になった言葉が多いです。これは、アルプスを擁するドイツやオーストリア、スイスでは、登山やスキーが非常に盛んだからです。
登山やスキーをする人なら、ドイツ語に由来する言葉・専門用語や用具の名前が多いことに気づくはずです。
Gärende/ゲレンデ
スキー場「Skigelände/シーゲレンデ」を略したドイツ語から日本語になった言葉。語源は、古高地ドイツ語「Lant=土地」。(現在のドイツ語の土地は「Land」)



Rucksack/リュックサック
リュックサックは、ドイツ語に由来する言葉。日本では略して「リュック」ということも多いですが、ドイツ語では「リュック」だけだと「背中」という意味。イギリス英語の「ラックサック」、アメリカ英語の「バックパック」も、実はドイツ語由来の英語です。

日本語になったドイツ語に由来する言葉【その他】
その他にも、日常生活のたくさんの言葉がドイツ語に由来する言葉だったりします。最近ではドイツ語を勉強する日本人は少なくなっていますが、ドイツ語由来の言葉は非常に日常的に使われているんですね。
Märchen/メルヘン
ドイツ語でも日本語と同じく、おとぎ話の中のような概念や、お話そのものを指します。ドイツで口承説話をまとめたグリム兄弟により、その概念が形作られたといわれています。

Autobahn/アウトバーン
日本でいう高速道路。ヒトラーによって着工が決定され、今日も利用されています。基本的には料金無料、速度制限がない区間もあり、100~130km出てる車が多いです。

Arbeit/アルバイト
ドイツ語に由来する言葉として、とても有名ですね。日本ではパートタイムの仕事をいいますが、ドイツ語では基本的にフルタイムを指します。ただし、「作業」や本業以外の仕事を「アルバイト」ということもあり、文脈によって使い方が異なります。

Gummi/グミ・ゴム
ゼラチンで果汁を固めたグミは、ドイツのハリボー社が初めて開発したもので、「グミ」はドイツ語から日本語になった言葉。ドイツ語では、「グミ」というと本来はゴムのことを指します。食べるグミを指すときは、「Gummibärchen/グミベアヒェン」(ハリボで最も人気の熊のグミ)または商品名ということが多いようです。


Baumkuchen/バウムクーヘン
ドイツ語のお菓子として、日本で最も有名な「バウム(木)クーヘン(ケーキ)」。ドイツ語に由来する言葉であることは言うまでもないでしょう。実は、このバウムクーヘン、ドイツではあまり食べられていません。

Seminar/ゼミナール
大学の「ゼミ」は、ドイツ語のゼミナールの略称。英語の「セミナー」に相当します。語源は、ラテン語「seminarium=神学校・種をまくこと」。
Thema/テーマ
話題、表題のこと。英語発音では「テーム」。発音からドイツ語に由来する言葉だと分かる一例です。



ドイツ語に由来する言葉は明治の若者言葉にも!
「最近の若者は正しい言葉も知らんで、なっとらん!」
こういう年配の方が稀によくいますが、彼らも若かりし頃はそう言われて年齢を重ねてきたのでしょう。
ほとんどの時代で、若者言葉や流行語というのは存在 します。参考:漫画アニメの中国人はなぜ「あるある」言う?お嬢様は「ですわ」?博士キャラは「~のじゃ」?
なんと明治時代には、ドイツ語由来の若者言葉も存在していました!


多言語から「お堅い」と評されるドイツ語と、日本語を合わせた当時の若者言葉を見ていきましょう!
ボリュームリッヒ
量が多いこと。英語の「ボリューム」にドイツ語の形容詞的な「lich/リッヒ」がつきました。

ドッペる
留年すること。今でいう「ダブる」。英語の「ダブル」に相当するドイツ語「doppele」から。ドッペルゲンガーのドッペルですね。


シェンなメッヒェン
シェンは「schön/美しい」メッヒェンは「Mädchen/娘」で美しい娘。ドイツ語らしい発音で言うなら、「シューンメテヒェン」。

ジンゲル
ドイツ語の「Sänger/ゼンガー」から転じて、芸者さん。ゼンガーは、歌手「Singer/ズィンガー」の複数形。厳密にいうと、ドイツ語で女性の歌手は「Siegerin/ズィンガリン」、複数形は「Sängerinnen/ゼンガリネン」です。
エトバス
男性器、女性器。ドイツ語の「etwas」は英語の「something」に当たる言葉なので、やらしい意味はありません。
ドイツ語由来「鳩時計」は間違いだった?

ドイツ語由来の日本語を一覧で見てきました。ドイツ語から日本語になった外来語には、意味が変わってしまった例がよくあります。
しかし、「鳩時計」は少し違った歴史を持ちます。
日本で鳩時計をドイツ人が見た時、「何でハト?」と聞かれることがあります。それもそのはず、鳩時計発祥の地とされるドイツで一般的なのは「カッコー時計(Kuckucksuhr/ククックスウアー)」だから。というより、鳩時計と呼ぶ国は、おそらく日本だけです。
ヨーロッパで時間を知らせる鳥といえば、カッコー。それなのに、なぜ日本語では鳩時計と呼ぶのでしょうか?
それは、日本で鳩時計が売り出される際のこと。閑古鳥と呼ばれるカッコーの名前を避け、代わりに鳩時計として売り出したため。


ということで、鳥のデザインや鳴き声自体も、より鳩らしいものが登場しています。忌み言葉を避けたがり、言葉に意味を持たせる日本の文化をよく表した例ですね。
参考:なぜ日本語には主語がないのか?主語・目的語を省略する3つの理由(「言霊」信仰の項目)

日本語になったドイツ語由来の言葉は意外とたくさん!
いかがでしょうか。意外と、ドイツ語由来の日本語というのは多いものです。
逆に、日本語からドイツ語になった言葉もあります。
参考:日本語由来の英語・外国語25選|海外で通じる世界共通語・英語になっている言葉・単語とは
少し前なら、医療や法律・電気工学系の学部でよく学ばれていたドイツ語。現在では、勉強する人は限られるようになりました。しかし、日本語のかなり日常的なところに使われるドイツ語は多いもの。
文法的に英語より難解な部分も多いとされますが、発音はむしろ英語より日本人がマスターしやすい言語です。
ぜひ、今回紹介した和製ドイツ語以外にも、いろいろ探してみてくださいね!
前回記事:ら抜き言葉はビジネスでNG⁉︎ら抜き言葉の法則・見分け方を間違いやすい例からご紹介
次回記事:ポルトガル語から日本語になった言葉16選
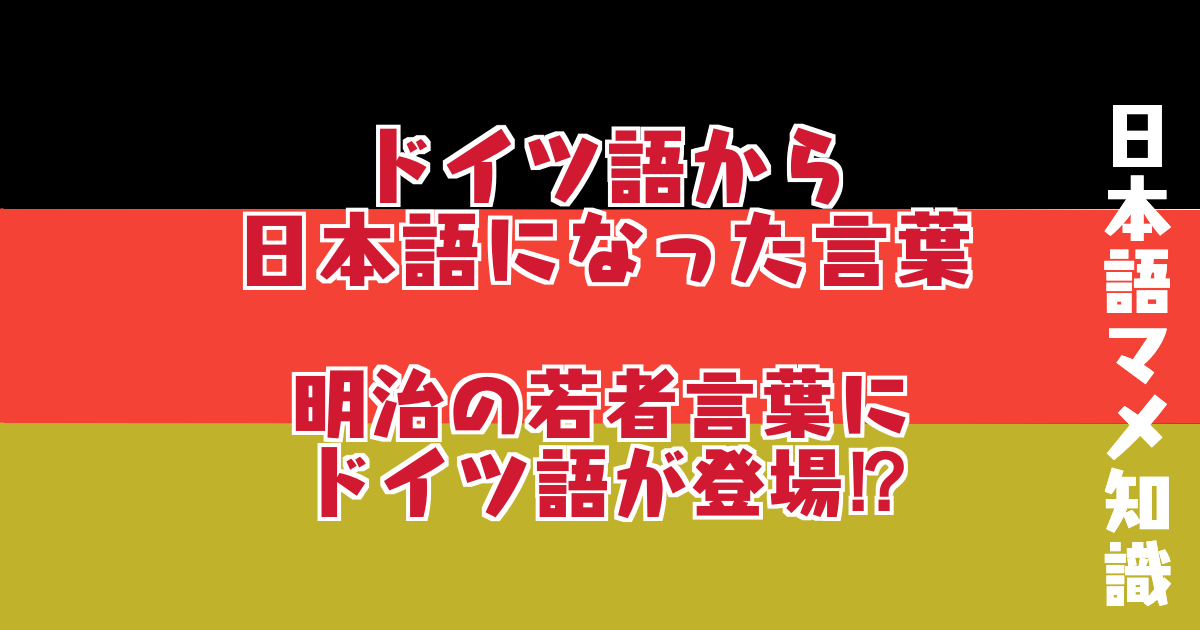
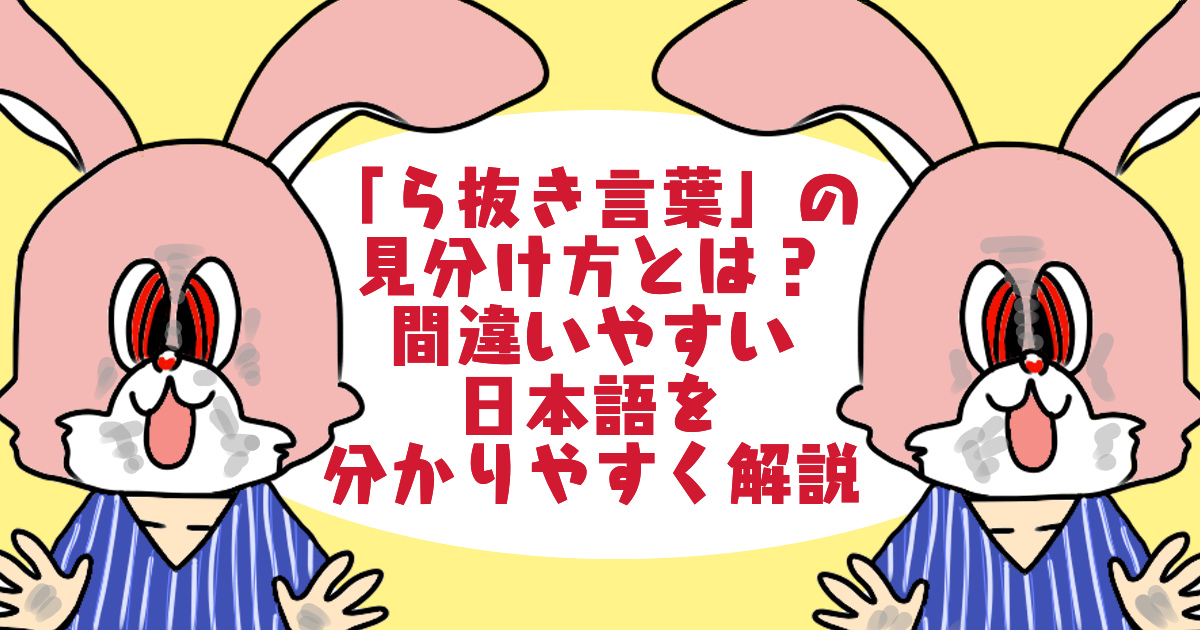
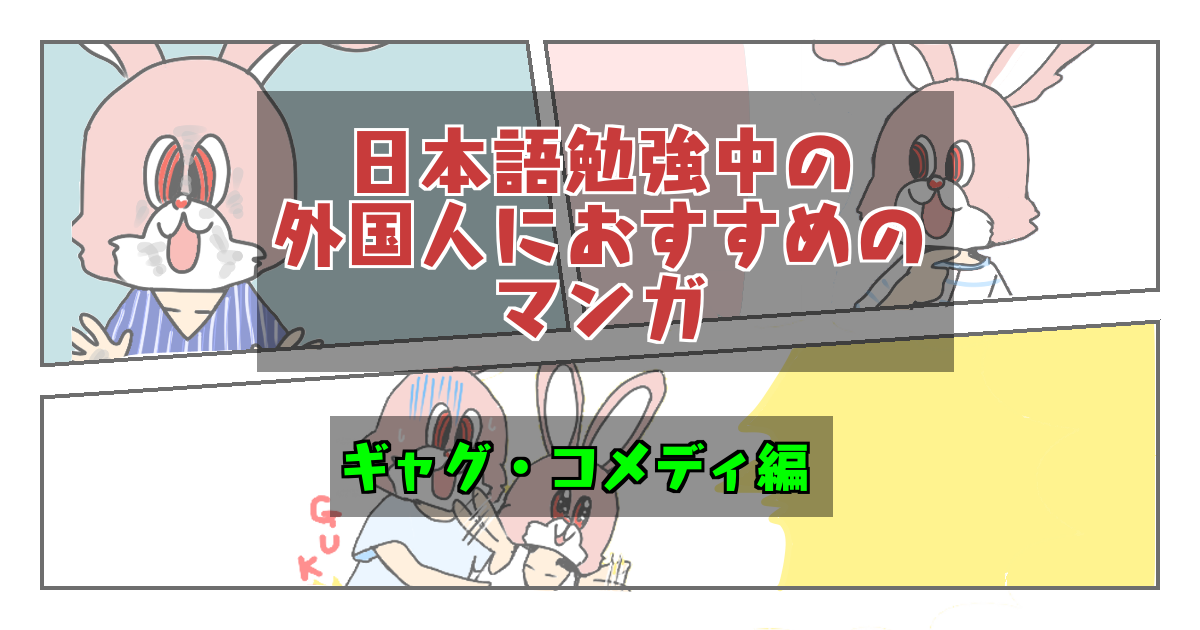
コメント