







日本人に馴染みの少ないサンスクリット語…と思われがちですが、実は、日本に大きな影響を与えたあるものが深く関わっています。
サンスクリット語とは?仏教用語とお経
さて、日本に大きな影響を与えた古代インドを起源とする「あるもの」とは、何でしょうか。
それは、仏教。仏教用語には、サンスクリット語由来の言葉がたくさんあります。
まずは、サンスクリット語とは何かを詳しく見ていきましょう。
サンスクリット語(梵語)とは
サンスクリット語(梵語)は、古代インドで使われていた言葉。
現在の母語話者数は少ないものの、インドの22の公用語のひとつとして認知されています。インドで多くの人が話すヒンズー語の成立に関わった言語です。
また、仏教、ヒンズー教、イスラム教、シーク教、ジャイナ教などの礼拝用言語として、世界中で使用されています。


サンスクリット語と日本語の共通点は?
日本語の仏教用語は、サンスクリット語と音に共通点があります。それは、音写されたものが多くあるから。
音写とは、音を当てて自国の言葉に訳すこと。
例えば、英語を耳で聞いてカタカナで「アイアム…」と書くのも音写です。逆に、日本語の音を英語圏の人がローマ字で書けば、それも音写です。
音写は、言語交換の過程で起きることで、特に使用する文字が異なる場合に起きやすいです。サンスクリット語と日本語では使う文字が異なり、ローマ字が世界で認知されていた時代ではなかったため、多くのサンスクリット語由来の音写された仏教用語が入ってきました。


参考:なぜ日本人は無宗教なの?いつから?初詣は神道式?葬儀は仏式?
ヒトラーもサンスクリット語ファン⁉︎
日本で寺を表す地図記号「卍」も、実はサンスクリット語由来。
近年、この地図記号を変えよう!という動きがあったのを覚えておいでですか?それは、欧米で「卍」といえば、ヒトラーやナチスドイツを連想させるから。




ナチで使用された逆卍は、もともと「幸福/おめでたいこと」を意味するサンスクリット語「卍」をヒトラーが真似たというのが通説です。



サンスクリット語のかっこいい言葉、名言一覧
サンスクリット語にはかっこいい言葉、名言がたくさんあります。明日使いたくなるサンスクリット語名言の日本語翻訳を見てみましょう。
「食べ物を他人に与えることは至高の慈善である。それよりも誉れ高いのは教育を他者に与えることである。」
「優しい言葉は、全ての動物を喜びで満たす。愛を込めた優しい言葉を使おう。言葉がなくなることはないのだから。」
「言葉は心によって、行動は言葉によって違うのだ。」
「地方によって言葉が違う、種によって芽が違う、土地によって水が違う、同じように、王によって民が違う。」
「他者の家族を自分の家族として尊重する人、他者の財産を欲しがらない人、全ての生き物を自分とみなし思いやれる人は、学者であり知恵がある人だ。」
かっこいい!サンスクリット語(梵語)由来の単語一覧
サンスクリット語というと、日本人にとって親しみが少ないように感じます。
しかし、サンスクリット語由来の言葉は、実は現代日本語でも使われています。そのほとんどが仏教用語のもの。
今の日本語にも残るサンスクリット語一覧を見ていきましょう!
阿吽(あうん)
息が合う様子を「阿吽の呼吸」といいますね。阿吽は、サンスクリット語由来の仏教用語。
梵語の字の表(日本語でいう五十音表)最初と最後の文字「a阿」「hūm吽」が語源。「全てのものと始まりと終わり」であり、「吐く息と吸う息」であることから、気持ちがひとつになる=「阿吽の呼吸」となりました。

アバター
インターネットサービスでユーザーの分身キャラクターである「アバター」は、サンスクリット語由来。英語にも残っていますね。
神仏の化身を意味する「अवतार(アヴァターラ)」が語源。

阿弥陀(あみだ)
大乗仏教の西方極楽浄土の仏のこと。日本では、浄土宗や浄土真宗の本尊のこと。
これらは、Amitāyus(アミタ)というサンスクリット語由来の言葉。


韋駄天(いだてん)
仏教における、軍神・護法神。ヒンドゥー教の神様Skanda(スカンダ)が変化したとされます。




億劫(おっくう)
面倒で気が進まないこと。漢語の「億」と「kalpa(コウ)」というサンスクリット語由来の合成語です。
もともとの「長い時間」の意味が転じて、簡単にはいかない面倒事という意味になりました。
娑婆(しゃば)
「シャバの空気は美味いぜ。」囚人(または囚人だった人)が外の世界の指していう「娑婆(しゃば/さば)」。
実は、サンスクリット語由来の仏教用語です。「sahā(サハー)」が語源。

達磨(だるま)
ダルマといえば、商売繁盛・開運出世の縁起物の丸い人形。南インドから中国にわたり、禅宗を伝えたとされる達磨大師を模した玩具です。
この菩提達磨は、「Boghi-Dharma」というサンスクリット語に由来します。

旦那(だんな)
夫の呼称「旦那(だんな)」は、仏教用語に由来。檀那(だんな)から来たもので、「दान(ダーナ)/布施」というサンスクリット語由来です。
寺の檀家(だんか)も、「ダーナ」が語源で、檀家制度が一般化したのは江戸時代とされています。



奈落(ならく)
仏教における地獄、また地獄に落ちること。
地獄を意味する「ナラカ」というサンスクリット語由来death。
人間(にんげん)
こちらでもやりましたが、人間も実はサンスクリット語由来の仏教用語。世間や人の世を表す「mamsya(マムシャ)」を漢語訳したものです。


花(はな)
「フラワー」の花…ではなく、芸能におけるおひねり「花」「花代」はサンスクリット語由来。
これは、「pana(パナ)/銅銭」というサンスクリット語からきた「波那」を京の色街で遊んだ代金の隠語として使用したことが語源。
般若(はんにゃ)
現代日本語ではそう使う機会はありませんが、鬼女の面を指して「般若の面」といいますね。また、それに近しい恐ろしい形相を、「般若のよう」と例えます。
これは、「prakñã/真実を見抜く智慧」の音写でサンスクリット語由来の言葉。

サンスクリット語由来の単語はかっこいい
いかがでしたか?サンスクリット語というと、全く耳馴染みのない言葉のように感じますが、実は仏教用語として多く日本語に入っています。
日本に入った時期が早いので、全て漢字の音写で日本語化しています。ポルトガル語由来・オランダ語由来以上に、意外な外来語があったのではないでしょうか?

英語やドイツ国民にまで影響を与えたサンスクリット語は世界に大きな影響を与えた言語のひとつ。そう考えるとかっこいいですね!
次回記事:
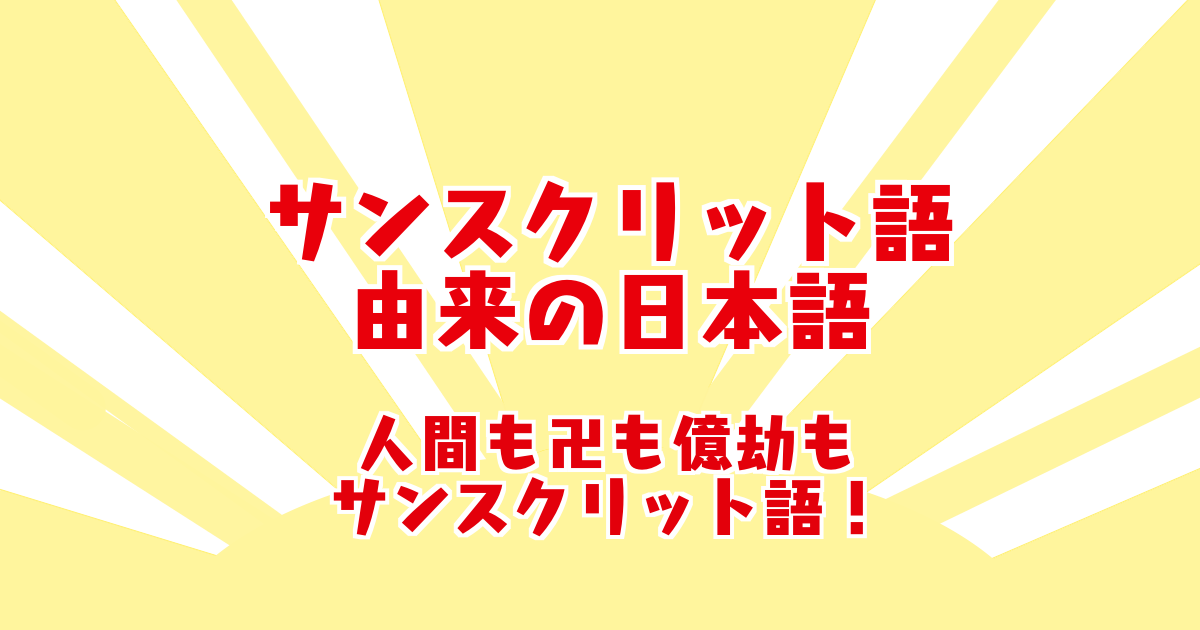
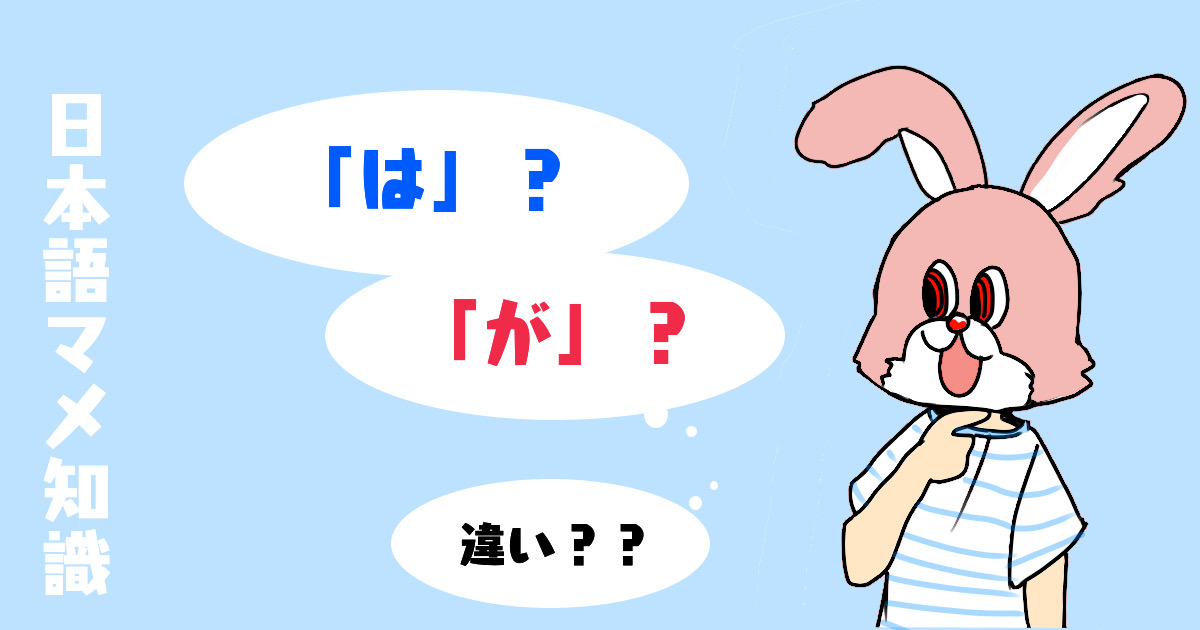
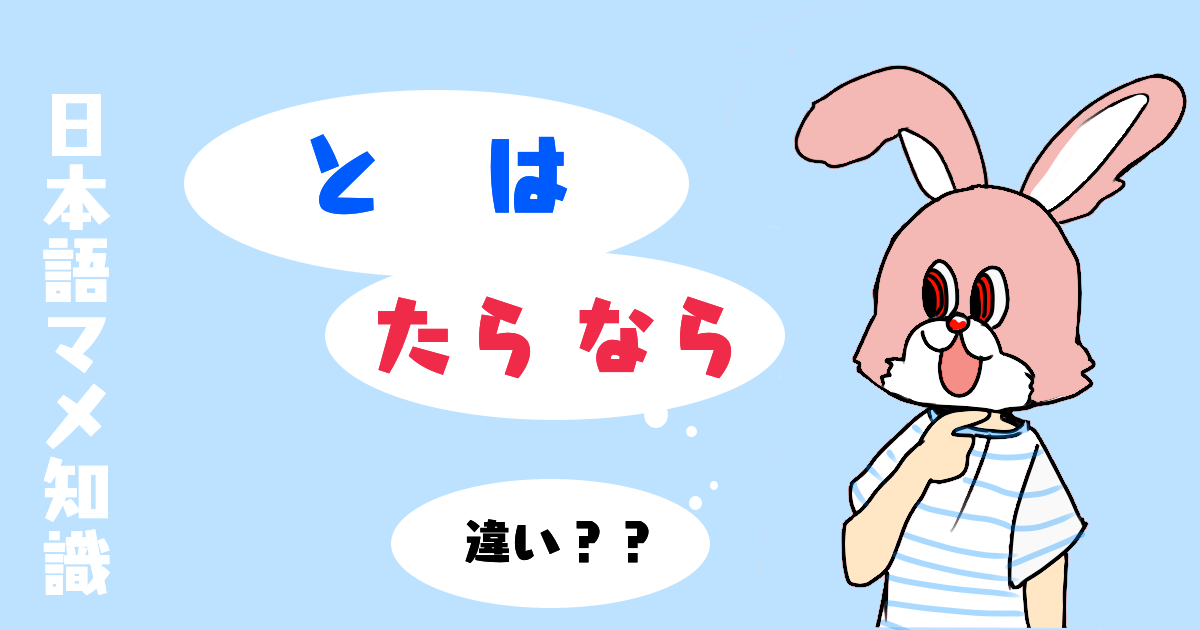
コメント